◆ 教員プレゼンバトル2013単位取得条件
受講生のみなさん、教員プレゼンバトル2013への出席大変お疲れ様でした。
異分野のプレゼンターの先生による発表をシャワーのように浴びて、多くの知識やプレゼンテクニックを学び取ることができたと思います。
最後に、本科目の成績評価方法を再度確認しておきたいと思います。
☆単位取得要件☆
1. 15名以上のプレゼンターの発表を聴講し、評価用紙を提出すること
2. 授業時間中における1回以上の質疑 (春学期a・b・c通して)
*雙峰祭開催「院生プレゼンバトル」の参加は3名分の出席とする
*履修申請を忘れずに!
以上のように、本科目は院生プレゼンバトル2013への参加を強く推奨しています。
次は、教員プレゼンバトルで吸収したプレゼンテクニックを実践する番です。
プレゼンター、また審査員として、皆さんの参加をお待ちしております。
教員プレゼンバトル
教員プレゼンバトル2013 第九回講義概要
◆ 原 尚人 先生 『放射性ヨウ素と小児甲状腺がん』
 原先生は医学医療系のご所属で、乳腺甲状腺内分泌外科学がご専門の先生です。
「放射性ヨウ素」、「甲状腺がん」など、原発事故と関連してよく使われるキーワードに注目が集まりました。原先生は、これらのキーワードに関して飛び交う情報によって混乱しがちな私たちに、正しい認識と接し方について教えて頂きました。
原発事故に伴う放射線の人体への影響を知る上で、チェルノブイリ事故が大きな示唆を与えると言います。放射線による汚染が拡大したチェルノブイリ地方において、様々な健康被害が引き起こされたと想像されますが、事故前に比べて患者の数が統計的に明らかに増加した病気は、甲状腺がんのみだそうです。
原先生はまず、甲状腺とヨウ素の関係について紹介されました。
体に取り込まれたヨウ素は必ず甲状腺に入ります。そして通常、甲状腺にはある一定量のヨウ素が蓄積されていきます。
ここで、もし放射性ヨウ素が甲状腺に多く蓄積されると、放射線によって遺伝子が傷つけられ、細胞はがん化してしまいます。特に、細胞分裂が活発な小児は大人に比べて、影響を受けやすいそうです。
しかし、ここ日本においては、今後小児甲状腺がんはほとんど増加しないだろう、と原先生は言います。日本人は普段から海産物を多くとっているため、ヨウ素が充足状態にあり、新たに放射性ヨウ素が入ってきても蓄積されることなく流れてしまうことが、理由の一つです。
また万が一、原発事故が拡大し、退避命令が出るような事態になった場合にも、「安定性ヨウ素剤」を飲むことで新たな放射性ヨウ素の蓄積を防ぐことができるそうです。安定性ヨウ素剤が手に入らなかったとしても、昆布や昆布菓子で代替できることは覚えておくといいでしょう。しかし、短期間に何度もヨウ素を摂取することは、逆に効果が減少する「エスケープ現象」を引き起こすため注意が必要なのだそうです。
日本においては、小児甲状腺がんに過剰に心配することはない、というのが結論のようです。チェルノブイリ地方は、海産物をほとんど口にしない地域であり、日本政府が実施しているような汚染地域のミルクの出荷制限も行われていなかったそうです。
一方、ポーランドでは、海に面している土地柄のため、海産物を食べる習慣がありました。そして、政府による安定性ヨウ素の配布やミルクの出荷制限をした結果、小児甲状腺がんは増えなかったことが報告されているそうです。また万が一、小児甲状腺がんを発症したとしても、小児甲状腺がんは出術で完治できるため、決して怖い病気ではないそうです。
原発事故は、依然収束したとは言い切れません。そんな中、氾濫する様々な情報によって、健康面での不安に駆られている人も多いと思います。しかし、遺伝と甲状腺の研究という医学的見地によって裏付けられた確かな主張と、懇切丁寧で分かりやすい説明により、放射性ヨウ素や、甲状腺がんに対する不安を軽減することができたと思います。
(文責:尾澤岬)
原先生は医学医療系のご所属で、乳腺甲状腺内分泌外科学がご専門の先生です。
「放射性ヨウ素」、「甲状腺がん」など、原発事故と関連してよく使われるキーワードに注目が集まりました。原先生は、これらのキーワードに関して飛び交う情報によって混乱しがちな私たちに、正しい認識と接し方について教えて頂きました。
原発事故に伴う放射線の人体への影響を知る上で、チェルノブイリ事故が大きな示唆を与えると言います。放射線による汚染が拡大したチェルノブイリ地方において、様々な健康被害が引き起こされたと想像されますが、事故前に比べて患者の数が統計的に明らかに増加した病気は、甲状腺がんのみだそうです。
原先生はまず、甲状腺とヨウ素の関係について紹介されました。
体に取り込まれたヨウ素は必ず甲状腺に入ります。そして通常、甲状腺にはある一定量のヨウ素が蓄積されていきます。
ここで、もし放射性ヨウ素が甲状腺に多く蓄積されると、放射線によって遺伝子が傷つけられ、細胞はがん化してしまいます。特に、細胞分裂が活発な小児は大人に比べて、影響を受けやすいそうです。
しかし、ここ日本においては、今後小児甲状腺がんはほとんど増加しないだろう、と原先生は言います。日本人は普段から海産物を多くとっているため、ヨウ素が充足状態にあり、新たに放射性ヨウ素が入ってきても蓄積されることなく流れてしまうことが、理由の一つです。
また万が一、原発事故が拡大し、退避命令が出るような事態になった場合にも、「安定性ヨウ素剤」を飲むことで新たな放射性ヨウ素の蓄積を防ぐことができるそうです。安定性ヨウ素剤が手に入らなかったとしても、昆布や昆布菓子で代替できることは覚えておくといいでしょう。しかし、短期間に何度もヨウ素を摂取することは、逆に効果が減少する「エスケープ現象」を引き起こすため注意が必要なのだそうです。
日本においては、小児甲状腺がんに過剰に心配することはない、というのが結論のようです。チェルノブイリ地方は、海産物をほとんど口にしない地域であり、日本政府が実施しているような汚染地域のミルクの出荷制限も行われていなかったそうです。
一方、ポーランドでは、海に面している土地柄のため、海産物を食べる習慣がありました。そして、政府による安定性ヨウ素の配布やミルクの出荷制限をした結果、小児甲状腺がんは増えなかったことが報告されているそうです。また万が一、小児甲状腺がんを発症したとしても、小児甲状腺がんは出術で完治できるため、決して怖い病気ではないそうです。
原発事故は、依然収束したとは言い切れません。そんな中、氾濫する様々な情報によって、健康面での不安に駆られている人も多いと思います。しかし、遺伝と甲状腺の研究という医学的見地によって裏付けられた確かな主張と、懇切丁寧で分かりやすい説明により、放射性ヨウ素や、甲状腺がんに対する不安を軽減することができたと思います。
(文責:尾澤岬)
◆ 岡田 幸彦 先生 『 「成功するサービス」の開発論理 』
 岡田先生は会計学を専門に研究なさっている先生です。今回は研究とは何かについて、そして成功するサービスに関する研究を発表していただきました。
岡田先生はまず、研究とは何かを語りました。岡田先生は一橋大学で社会科学とは何かを身につけ、研究なさっているそうです。まず、研究とは「誰も知らないことを明らかにする」ことであると話します。社会科学では全てが仮説で構成されますが、その仮説も過去を検証するだけではなくこれからの役に立つことが、重要なのだと強調します。
"How many papers do you have?"ではなく"What is your best paper?"が信条であると岡田先生は語ります。そして、2013年現在における岡田先生のbest paperが今回のテーマである「成功するサービス」の開発論理です。
会場ではサービス分野における原価企画のモデル化、そして実証研究をどのように行ったかを明朗な語り口でプレゼンされました。
製造業の常識では「原価を発生させるのは企業であり、価値を発生させるのは顧客である」とされています、サービス業ではそれに加えて「原価に顧客が影響を及ぼし、価値に企業が影響を及ぼす」ことが予想されました。守秘義務があるため具体的な企業名は明かされませんでしたが、岡田先生は自ら立てた仮説を高業績事業者十八社の協力を得て、この予想が実際に成功する企業において共通していることを明らかにしました。
先生は発表においてまだまだこれからも研究を続けていくことを、そして自らが「成功するサービス」の理論に基づいた行動を続けながら活動することを臭わせながら、発表を終えました。
「私はプレゼンテーションの教育を受けていないので、プレゼンテーションの参考にはならないと思う」と話した岡田先生でしたが、内容と熱意を同時に伝えるプレゼンは非常に学ぶところの多いものでした。
『種明かし』
種明かしディスカッションにおいて、「種明かしコース」と「本番コース」のどちらがいいかを岡田先生は尋ねられました。
会場では「本番コース」を希望するものが多く、「本番コース」が実施されました。その詳細はこちらでは書くことが出来ませんが、一端を http://www.sk.tsukuba.ac.jp/new_shako/ から読むことが出来ます。
(シス情・社会工学専攻の若宮浩司さんに概要の執筆をしていただきました)
岡田先生は会計学を専門に研究なさっている先生です。今回は研究とは何かについて、そして成功するサービスに関する研究を発表していただきました。
岡田先生はまず、研究とは何かを語りました。岡田先生は一橋大学で社会科学とは何かを身につけ、研究なさっているそうです。まず、研究とは「誰も知らないことを明らかにする」ことであると話します。社会科学では全てが仮説で構成されますが、その仮説も過去を検証するだけではなくこれからの役に立つことが、重要なのだと強調します。
"How many papers do you have?"ではなく"What is your best paper?"が信条であると岡田先生は語ります。そして、2013年現在における岡田先生のbest paperが今回のテーマである「成功するサービス」の開発論理です。
会場ではサービス分野における原価企画のモデル化、そして実証研究をどのように行ったかを明朗な語り口でプレゼンされました。
製造業の常識では「原価を発生させるのは企業であり、価値を発生させるのは顧客である」とされています、サービス業ではそれに加えて「原価に顧客が影響を及ぼし、価値に企業が影響を及ぼす」ことが予想されました。守秘義務があるため具体的な企業名は明かされませんでしたが、岡田先生は自ら立てた仮説を高業績事業者十八社の協力を得て、この予想が実際に成功する企業において共通していることを明らかにしました。
先生は発表においてまだまだこれからも研究を続けていくことを、そして自らが「成功するサービス」の理論に基づいた行動を続けながら活動することを臭わせながら、発表を終えました。
「私はプレゼンテーションの教育を受けていないので、プレゼンテーションの参考にはならないと思う」と話した岡田先生でしたが、内容と熱意を同時に伝えるプレゼンは非常に学ぶところの多いものでした。
『種明かし』
種明かしディスカッションにおいて、「種明かしコース」と「本番コース」のどちらがいいかを岡田先生は尋ねられました。
会場では「本番コース」を希望するものが多く、「本番コース」が実施されました。その詳細はこちらでは書くことが出来ませんが、一端を http://www.sk.tsukuba.ac.jp/new_shako/ から読むことが出来ます。
(シス情・社会工学専攻の若宮浩司さんに概要の執筆をしていただきました)
◆ 逸村 裕 先生 『学術情報・成果発表・オープンアクセス』
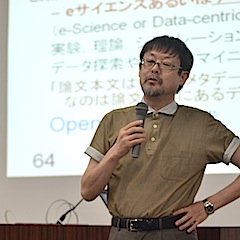 逸村先生は図書館情報メディア系で学術情報基盤を専門とされていますが、本講義の担当教員ということでもあり、最後にふさわしいプレゼンとなりました。
本講義を受講している大学院生をはじめとした研究者にとって、研究論文といった研究成果をどうやって公表していくか、またどうしたらよい評価を受けられるかということが問題となっています。
そんな中で評価の指標として誤用されているImpact Factorがあります。
具体例として2012年のImpact Factorは (2010年~2011年にある雑誌に掲載された論文が2012年に引用されたのべ回数) / (2010年-2011年の間に掲載された論文数)として算出されます。
Impact Factorはあくまで学術雑誌の指標であり、研究者に関する評価ではありませんが研究者の指標として誤用されています。さらにまた近年SNSを利用した論文に対する指標など新しい評価指標が新しくつぎつぎと生まれています。
そのため、このような評価指標は本質的に何を表しているのか、どんな意味があるのかしっかりと考えて使わなければなりません
続いて、研究を進めていく上で論文を読むことも重要です、しかし近年、学術雑誌は電子化などの流れから価格高騰が止まりません。大学図書館のような研究者のために学術雑誌や論文を契約する機関にとって非常に厳しくなっています。しかし、一方でオープンアクセスという出版形態が出てきています。オープンアクセス誌は利用者がお金を払うことなく論文にアクセスすることができます。背景に「研究は税金をもとにして行われているのだから、研究成果は国民に無償で公表されて当然である」と意識があります。オープンアクセスにもいくつかの手段があり、大学自体がもっとも身近なものとしては機関リポジトリを挙げることができます。
日本の学術情報流通の観点からみるとオープンアクセスのような情報をオープンにしていくことや研究に使われたデータを共有することに関して海外と比べ動きが遅いのが現状です。こういった学術情報が爆発的に増えていく中でこれから学術情報やその流通がどうなっていくのか研究者である私たち自身が考えていく必要があると最後には強く訴えかけられていました。
研究分野に関わらず共通する研究成果をどうやって世に出していくかという問題を改めて考えさせられるプレゼンとなっていました。
また、発表時間15分ジャストで終了し、1秒も誤差の無い時間配分はみごとでした。
逸村先生のプレゼンは仕掛けや種がある、聴衆を飽きさせないプレゼントで、ストーリがしっかりとあるので、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
(文責:野沢健人)
逸村先生は図書館情報メディア系で学術情報基盤を専門とされていますが、本講義の担当教員ということでもあり、最後にふさわしいプレゼンとなりました。
本講義を受講している大学院生をはじめとした研究者にとって、研究論文といった研究成果をどうやって公表していくか、またどうしたらよい評価を受けられるかということが問題となっています。
そんな中で評価の指標として誤用されているImpact Factorがあります。
具体例として2012年のImpact Factorは (2010年~2011年にある雑誌に掲載された論文が2012年に引用されたのべ回数) / (2010年-2011年の間に掲載された論文数)として算出されます。
Impact Factorはあくまで学術雑誌の指標であり、研究者に関する評価ではありませんが研究者の指標として誤用されています。さらにまた近年SNSを利用した論文に対する指標など新しい評価指標が新しくつぎつぎと生まれています。
そのため、このような評価指標は本質的に何を表しているのか、どんな意味があるのかしっかりと考えて使わなければなりません
続いて、研究を進めていく上で論文を読むことも重要です、しかし近年、学術雑誌は電子化などの流れから価格高騰が止まりません。大学図書館のような研究者のために学術雑誌や論文を契約する機関にとって非常に厳しくなっています。しかし、一方でオープンアクセスという出版形態が出てきています。オープンアクセス誌は利用者がお金を払うことなく論文にアクセスすることができます。背景に「研究は税金をもとにして行われているのだから、研究成果は国民に無償で公表されて当然である」と意識があります。オープンアクセスにもいくつかの手段があり、大学自体がもっとも身近なものとしては機関リポジトリを挙げることができます。
日本の学術情報流通の観点からみるとオープンアクセスのような情報をオープンにしていくことや研究に使われたデータを共有することに関して海外と比べ動きが遅いのが現状です。こういった学術情報が爆発的に増えていく中でこれから学術情報やその流通がどうなっていくのか研究者である私たち自身が考えていく必要があると最後には強く訴えかけられていました。
研究分野に関わらず共通する研究成果をどうやって世に出していくかという問題を改めて考えさせられるプレゼンとなっていました。
また、発表時間15分ジャストで終了し、1秒も誤差の無い時間配分はみごとでした。
逸村先生のプレゼンは仕掛けや種がある、聴衆を飽きさせないプレゼントで、ストーリがしっかりとあるので、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
(文責:野沢健人)
教員プレゼンバトル2013 第八回講義概要
◆ 麻見直美 先生 「 體 」
 麻見先生はスポーツ栄養の研究をなさっています。骨の代謝に対する運動と栄養の影響を、研究室でお持ちのデータを中心にご紹介いただきました。
骨は大人になっても常に作り替えられている、ダイナミックな臓器であり、様々な要因が関わってきています。
そのなかでも特に運動が骨に良い影響があるとされています。動物(ラット)を使った運動負荷実験の結果からも運動の骨への影響は明らかです。
運動が走行運動でも水泳運動であっても骨密度を上げることが分かっているようです。
人間のデータでも運動の骨への影響は明らかです。平均よりも骨密度が高い人は、活動量が多い事もわかっています。適切な運動は骨密度を高めるのです。
しかし、アスリート(運動をしている人)でも骨密度が高い人と普通の人がいるそうです。その原因を探るために、食事バランスガイドを用いて食
骨密度が高い人は食事のバランスが良く、骨密度の普通の人はのバランスが悪いことがわかりました。
アスリートにおける骨密度の違いは食事バランスの違いによるものだったようです。自身のからだは自身の食べた者でできています。適切な運動と食事が骨を豊にし、からだをつくるのです。
質疑応答でのやりとりを1つ紹介します。
Q、栄養のバランスとは人によって違うのではないのか、どのように栄養状況を評価しているのか。(システム情報系の教員)
A、正確に評価することは現実的には難しい。栄養状況を正確に判断できる指標はまだ確立できていない。血液が1つの指標であるが、アスリートだと血液等で栄養状況を評価するのは難しい。骨を評価することで集大成的な評価が出来る。
(文責:角谷雄哉)
麻見先生はスポーツ栄養の研究をなさっています。骨の代謝に対する運動と栄養の影響を、研究室でお持ちのデータを中心にご紹介いただきました。
骨は大人になっても常に作り替えられている、ダイナミックな臓器であり、様々な要因が関わってきています。
そのなかでも特に運動が骨に良い影響があるとされています。動物(ラット)を使った運動負荷実験の結果からも運動の骨への影響は明らかです。
運動が走行運動でも水泳運動であっても骨密度を上げることが分かっているようです。
人間のデータでも運動の骨への影響は明らかです。平均よりも骨密度が高い人は、活動量が多い事もわかっています。適切な運動は骨密度を高めるのです。
しかし、アスリート(運動をしている人)でも骨密度が高い人と普通の人がいるそうです。その原因を探るために、食事バランスガイドを用いて食
骨密度が高い人は食事のバランスが良く、骨密度の普通の人はのバランスが悪いことがわかりました。
アスリートにおける骨密度の違いは食事バランスの違いによるものだったようです。自身のからだは自身の食べた者でできています。適切な運動と食事が骨を豊にし、からだをつくるのです。
質疑応答でのやりとりを1つ紹介します。
Q、栄養のバランスとは人によって違うのではないのか、どのように栄養状況を評価しているのか。(システム情報系の教員)
A、正確に評価することは現実的には難しい。栄養状況を正確に判断できる指標はまだ確立できていない。血液が1つの指標であるが、アスリートだと血液等で栄養状況を評価するのは難しい。骨を評価することで集大成的な評価が出来る。
(文責:角谷雄哉)
◆ 外山美樹 先生 「悲観主義って本当に悪いの?」
外山先生のプレゼンはチェック票への記入からはじまりました。
チェック票を使ってベストを尽くしたいと思う状況を思い浮かべて、
その状況であなたがどういう準備をするのかを聴衆に回答さたのです。
このチェック票は、たぶんうまくいくと思っていてもまずは最悪の状況を予想する「防衛的悲観主義」を見極めるためのものだそう。
これまでは、楽観主義者が悲観主義者と比較して、動機付けが高いやパフォーマンスが高いとされてきた。しかし、外山先生は絶好調期のイチロー選手の名言をもとに悲観主義でも高いパフォーマンスを発揮することは可能だといいます。
特に、「防衛的悲観主義」に関する研究をなさっているそうです。
防衛的悲観主義者はどのようにパフォーマンスを高めているのでしょうか。ダーツのパフォーマンスにかんする研究が紹介されました。防衛的悲観主義者はダーツの前に成功したところをイメージさせたり、リラックスさせたりするよりも、失敗している状況をイメージしたときにパフォーマンスが高まるのです。
このことは、ダーツだけではなく他の方法でパフォーマンスを測定しても同じことが言えるそうです。
スライドのデザインが美しく、プレゼンもそれに合わせて流れる様にすすめられました。スライドの凝ったアニメーションに対しては歓声が上がるほどでした。外山先生はデザインなども独学で学ばれ、スライド作りに活かされているようです。今回のパフォーマンス(プレゼン)に対して、先生自身は防衛的悲観主義だったのでしょうか。
質疑応答でなされたやりとりを1つ紹介します。
Q、何歳くらいから決まってくるのか、外的要因はなんなのか。自分の意識で替えられるのか。
A、中学生や小学生高学年では確立している。外的要因としては様々なことが関わっている。人によって違うのではなく、行動(パフォーマンス)によって考え方がちがう。ある行動に対する、方略・方法のことを拾っている。
(文責:角谷雄哉)
◆ 松島亘志 先生 「イトカワから考える固体粒子系物理」
[プレゼン発表]
 松島先生は、システム情報系で粒状体力学・地盤工学を専門に研究している先生です。今回は、以前話題となった衛星「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の“粒子”に関する研究を紹介されました。
小惑星イトカワの表面は、ゴツゴツした岩塊のイメージがありますが、度重なる隕石の衝突によって細粒化した粒子がたくさん存在します。はやぶさ計画では、この粒子を回収することに成功したことで、大きく盛り上がりました。
はやぶさが回収した飼料は、国内外の様々な研究グループによって解析されましたが、松島先生は、「粒子の大きさや形状」に着目する研究を行いました。
解析で分かったことは、イトカワの粒子の大きさの分布は、「フラクタル」を示すということでした。言い換えると、イトカワの表層の写真を、様々な長さの尺度で撮影しても、どれもそっくり同じに見えるということです。
実はこのフラクタルという性質は、イトカワの表面の粒子だけでなく、月や地球上の粒子の大きさ分布など、様々な所に顔を出す、とても普遍的なものだそうです。このことは、隕石が衝突して、細粒化される際のプロセスの類似性を示唆します。
しかし、イトカワと月や地球の粒子では、同じフラクタル性を示しても、フラクタルを特徴づける数字がわずかに異なっているそうです。そして、この辺りの微妙な違いが、今後に向けて興味を駆り立てる研究対象なのだそうです。
イトカワの表面という壮大な宇宙での出来事が、地球上での身近な出来事と、フラクタルという性質でみごとに繋がった瞬間、とてもぞくぞくしました。本研究は、学術的にも非常に高い評価を受けており、今後の研究の発展が期待されます。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 試料の解析というと、粒子の「組成」の分析がメインだと思ってしまうが、「粒子の大きさや形」を解析することでも、いろいろと面白いことがわかるのか。(生命環境科学研究科の教員)
A. 大きさや、形状を調べるという簡単な解析でも、面白い結果は出てくる。比較的単純なルールに物事が支配されていることを反映していると思う。
Q. はやぶさが持ってきたイトカワの粒子はごく少数であったと聞いたが、実際どの程度か。(農学が専門の大学院生)
A. はやぶさが持ち帰った容器を、トントンと叩いて取り出した粒子が40個。それよりも小さくて、容器からヘラで掻き出して取った粒子が1469個。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
(文責:尾澤岬)
松島先生は、システム情報系で粒状体力学・地盤工学を専門に研究している先生です。今回は、以前話題となった衛星「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の“粒子”に関する研究を紹介されました。
小惑星イトカワの表面は、ゴツゴツした岩塊のイメージがありますが、度重なる隕石の衝突によって細粒化した粒子がたくさん存在します。はやぶさ計画では、この粒子を回収することに成功したことで、大きく盛り上がりました。
はやぶさが回収した飼料は、国内外の様々な研究グループによって解析されましたが、松島先生は、「粒子の大きさや形状」に着目する研究を行いました。
解析で分かったことは、イトカワの粒子の大きさの分布は、「フラクタル」を示すということでした。言い換えると、イトカワの表層の写真を、様々な長さの尺度で撮影しても、どれもそっくり同じに見えるということです。
実はこのフラクタルという性質は、イトカワの表面の粒子だけでなく、月や地球上の粒子の大きさ分布など、様々な所に顔を出す、とても普遍的なものだそうです。このことは、隕石が衝突して、細粒化される際のプロセスの類似性を示唆します。
しかし、イトカワと月や地球の粒子では、同じフラクタル性を示しても、フラクタルを特徴づける数字がわずかに異なっているそうです。そして、この辺りの微妙な違いが、今後に向けて興味を駆り立てる研究対象なのだそうです。
イトカワの表面という壮大な宇宙での出来事が、地球上での身近な出来事と、フラクタルという性質でみごとに繋がった瞬間、とてもぞくぞくしました。本研究は、学術的にも非常に高い評価を受けており、今後の研究の発展が期待されます。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 試料の解析というと、粒子の「組成」の分析がメインだと思ってしまうが、「粒子の大きさや形」を解析することでも、いろいろと面白いことがわかるのか。(生命環境科学研究科の教員)
A. 大きさや、形状を調べるという簡単な解析でも、面白い結果は出てくる。比較的単純なルールに物事が支配されていることを反映していると思う。
Q. はやぶさが持ってきたイトカワの粒子はごく少数であったと聞いたが、実際どの程度か。(農学が専門の大学院生)
A. はやぶさが持ち帰った容器を、トントンと叩いて取り出した粒子が40個。それよりも小さくて、容器からヘラで掻き出して取った粒子が1469個。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
(文責:尾澤岬)
教員プレゼンバトル2013 第七回講義概要
◆坪内孝司先生 「採石場における小割作業の自動化に向けた取り組み」
[プレゼン発表]
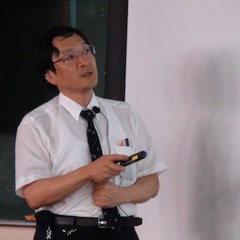 坪内先生は、システム情報系の知能ロボットの研究がご専門の先生です。今回のプレゼンでは、坪内先生自身が、過去の学会の口頭発表で“実際に使用した”スライドを使って発表されました。
先生のプレゼン内容を簡潔に言うと、それはまさにタイトルの通りでした。「名は体を表す」というコンセプトのもとで、タイトルの選定には充分推敲されているそうです。
コンクリートの骨材として使われる石灰石は、建築の現場では欠かせない材料です。ですが、この石灰石を採石するには、非常に大きな手間がかかります。まずは、石灰石鉱山で爆薬を用いた発破を行い、大きなゴロゴロとした石灰石の岩に砕きます。その後、運びやすいように、この岩を小さく割る作業(小割)をします。最後に、小割して運びやすくなった石灰石を輸送し、所望の場所まで届けます。
非常に重く、ゴロゴロと不規則な動きをする石灰石の岩を、ショベルカーでコントロールし、小割する作業には、熟練した操作が必要です。また、石灰石の不規則な動きは、輸送の際にもしばしば、突発的な渋滞を引き起こします。
先生の研究は、これらの操作を知能ロボットの技術を用いて自動化しようという試みです。具体的には、ロボットに石灰石を認識させ、アームの自動制御を用いて石灰石を移動させる技術や、画像処理技術を応用し、輸送の際の渋滞箇所を検知する技術の開発を進めています。
現在、屋内での実験を繰り返し、改良を重ねている段階だそうですが、坪内先生らの開発した技術が、採石現場で活躍する日も刻々と近づいている模様です。
多くの受講生にとって、プレゼンの主な機会は、学会や研究会だと思います。なので、実際の学会での発表を元にした、坪内先生のプレゼンは、スライドづくりや、発表のリズム等、そのままお手本となるものでした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. ヒトが作業する場合と、ロボットに自動化させる場合では、現状では効率はどれくらいか?(数理物質科学研究科の大学院生)
A. 現状では、ヒトが作業した場合の7割ほどの効率である。熟練したヒトは、岩のどこをつつけば効率よく動かせるか分かっている。ロボットはそれがまだできていない。このことは今後の課題でもある。
Q. 岩を転がす際のショベルが一本指なのは理由があるか?二本指の方が効率が良い気がするが。(体育科学が専門の大学院生)
A. 一本指が昔から使われているから仕方がない。今この指の部分を作っているのは一社のみ。この規格を変更することは、コスト的に非常に難しくなっている。なので、この規格を前提にして自動化の研究を進めている。
坪内先生は、システム情報系の知能ロボットの研究がご専門の先生です。今回のプレゼンでは、坪内先生自身が、過去の学会の口頭発表で“実際に使用した”スライドを使って発表されました。
先生のプレゼン内容を簡潔に言うと、それはまさにタイトルの通りでした。「名は体を表す」というコンセプトのもとで、タイトルの選定には充分推敲されているそうです。
コンクリートの骨材として使われる石灰石は、建築の現場では欠かせない材料です。ですが、この石灰石を採石するには、非常に大きな手間がかかります。まずは、石灰石鉱山で爆薬を用いた発破を行い、大きなゴロゴロとした石灰石の岩に砕きます。その後、運びやすいように、この岩を小さく割る作業(小割)をします。最後に、小割して運びやすくなった石灰石を輸送し、所望の場所まで届けます。
非常に重く、ゴロゴロと不規則な動きをする石灰石の岩を、ショベルカーでコントロールし、小割する作業には、熟練した操作が必要です。また、石灰石の不規則な動きは、輸送の際にもしばしば、突発的な渋滞を引き起こします。
先生の研究は、これらの操作を知能ロボットの技術を用いて自動化しようという試みです。具体的には、ロボットに石灰石を認識させ、アームの自動制御を用いて石灰石を移動させる技術や、画像処理技術を応用し、輸送の際の渋滞箇所を検知する技術の開発を進めています。
現在、屋内での実験を繰り返し、改良を重ねている段階だそうですが、坪内先生らの開発した技術が、採石現場で活躍する日も刻々と近づいている模様です。
多くの受講生にとって、プレゼンの主な機会は、学会や研究会だと思います。なので、実際の学会での発表を元にした、坪内先生のプレゼンは、スライドづくりや、発表のリズム等、そのままお手本となるものでした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. ヒトが作業する場合と、ロボットに自動化させる場合では、現状では効率はどれくらいか?(数理物質科学研究科の大学院生)
A. 現状では、ヒトが作業した場合の7割ほどの効率である。熟練したヒトは、岩のどこをつつけば効率よく動かせるか分かっている。ロボットはそれがまだできていない。このことは今後の課題でもある。
Q. 岩を転がす際のショベルが一本指なのは理由があるか?二本指の方が効率が良い気がするが。(体育科学が専門の大学院生)
A. 一本指が昔から使われているから仕方がない。今この指の部分を作っているのは一社のみ。この規格を変更することは、コスト的に非常に難しくなっている。なので、この規格を前提にして自動化の研究を進めている。
◆鈴木義和先生 「静電噴霧熱分解法: 装置づくりからナノ材料の合成まで」
[プレゼン発表]
 鈴木先生は、無機系エネルギー・環境材料の研究者です。
自身でおっしゃるように“こてこての大阪人”で、芸人さながら、「どうも~~」と会場入りし、聴衆を沸かせました。
鈴木先生は、自身が経験した、研究室の立ち上げ、新規研究分野への参入をストーリー形式で紹介されました。研究室の立ち上げ時や、新規研究分野へ参入する際には、往々にして予算があまりなく、最新の実験機器を買うことができません。そんなとき、「自分たちで装置を自作する」という気概が大事だと鈴木先生は言います。
さらに、苦労して装置を自作することで、ブラックボックス化しがちな装置の扱いから脱却し、市販の装置ではできないパラメータの調整が可能になる等のメリットもあるそうです。
プレゼンのキーワードである「静電噴霧」とは、微細なナノ粒子をつくる手法のひとつです。非常に細いノズルから、電圧を印加した液体を吹きつけることで、大きさの均一な微粒子をつくることができます。そして、この均一な微粒子は、ナノ材料として幅広い応用の可能性を秘めています。
今まで、教員プレゼンバトルでプレゼンされた方の中でもダントツにエンターテイメント性のあるプレゼンでした。例えば、プレゼン途中でクイズを出し、正解者に研究室オリジナルのシールを配るなど、教員プレゼンバトルでしかできないような面白ネタが満載でした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 単一の大きさの微粒子が作成できると、どのような点が応用としてうれしいか?(教育学専攻の大学院生)
A. 身近な例では、ディスプレイの開発に役立っている。また、球状の形状は表面積が大きいため触媒として使用する応用が考えられる。
Q. 私は今、音響の研究をやっていて、自作のマイクを作っている。実際はなかなか思った通りの動作をしてくれない。装置を自作する際に、何か工夫していることはあるか?(音響工学が専門の大学院生)
A. 一般に、私の研究対象である材料系は、機械系に比べて、大きく測定値が異なるということはあまりないが、導電性が桁はずれに違ってくるということがまれにある。そういうときは、一見すると関係なさそうなパラメータも再度考え直してみる、という方針でいる。
鈴木先生は、無機系エネルギー・環境材料の研究者です。
自身でおっしゃるように“こてこての大阪人”で、芸人さながら、「どうも~~」と会場入りし、聴衆を沸かせました。
鈴木先生は、自身が経験した、研究室の立ち上げ、新規研究分野への参入をストーリー形式で紹介されました。研究室の立ち上げ時や、新規研究分野へ参入する際には、往々にして予算があまりなく、最新の実験機器を買うことができません。そんなとき、「自分たちで装置を自作する」という気概が大事だと鈴木先生は言います。
さらに、苦労して装置を自作することで、ブラックボックス化しがちな装置の扱いから脱却し、市販の装置ではできないパラメータの調整が可能になる等のメリットもあるそうです。
プレゼンのキーワードである「静電噴霧」とは、微細なナノ粒子をつくる手法のひとつです。非常に細いノズルから、電圧を印加した液体を吹きつけることで、大きさの均一な微粒子をつくることができます。そして、この均一な微粒子は、ナノ材料として幅広い応用の可能性を秘めています。
今まで、教員プレゼンバトルでプレゼンされた方の中でもダントツにエンターテイメント性のあるプレゼンでした。例えば、プレゼン途中でクイズを出し、正解者に研究室オリジナルのシールを配るなど、教員プレゼンバトルでしかできないような面白ネタが満載でした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 単一の大きさの微粒子が作成できると、どのような点が応用としてうれしいか?(教育学専攻の大学院生)
A. 身近な例では、ディスプレイの開発に役立っている。また、球状の形状は表面積が大きいため触媒として使用する応用が考えられる。
Q. 私は今、音響の研究をやっていて、自作のマイクを作っている。実際はなかなか思った通りの動作をしてくれない。装置を自作する際に、何か工夫していることはあるか?(音響工学が専門の大学院生)
A. 一般に、私の研究対象である材料系は、機械系に比べて、大きく測定値が異なるということはあまりないが、導電性が桁はずれに違ってくるということがまれにある。そういうときは、一見すると関係なさそうなパラメータも再度考え直してみる、という方針でいる。
◆佐藤正美先生 「排便障害はいかにQOLを低下させるか」
[プレゼン発表]
 佐藤先生は、医学医療系の先生です。研究と同時に、臨床の現場にも携わっています。看護系の先生が、この教員プレゼンバトルで話すのは初めてでした。なので、どんな話をするのだろうか、と受講生はとても興味を持ったと思います。
そんな多くの受講生にとって、未知の世界である看護学への入り口として、佐藤先生はまず、「看護的な人間の捉え方」について紹介されました。看護に携わる人は、人間を分析的ではなく、トータルに、そして統合的に捉えているそうです。
佐藤先生が、今回発表された研究テーマは、「直腸がん前方切除術後の排便障害を評価」です。日本人の死因のトップは、がんと言われています。がんの中にも、胃がんや肺がんなど、様々な種類がありますが、「直腸がん」は、数あるがんのなかでも死因の上位に位置するものだそうです。
直腸がんの治療に、直腸の前方を切除するというものがあります。このような手術を受けた患者さんは、普段の生活に欠かせない排便に苦労することも多いそうです。例えば、私たちは、オナラか便のどちらが出そうなのかということを感覚的に分かります。なぜかというと、肛門付近に、両者を感知するサンプリングセンサーが付いているからだそうです。しかし、直腸がん前方切除術を受けた患者さんには、このセンサーは働かないため、大きな障害を伴います。
佐藤先生は、このような患者さんへのアンケートや、排便行動の定量的な評価、文献調査を駆使し、患者さんのQOLの向上を目指して日々研究しています。
人間をトータルに捉えるという看護の性格から、プレゼンには、悲しい局面や幸せな局面など、人間の感情的な内容が多く含まれていました。佐藤先生は、これらの喜怒哀楽を、発話の強弱や、トーンでみごとに表現していました。そして何より、患者さんへの愛が存分に伝わってくる発表でした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 海外によってトイレ事情が大きく異なる。海外に行くと、つくづく日本はトイレ事情に恵まれていると思う。すると、国によって排便障害への捉え方が変わってくるのではないか。(数理物質系の教員)
A.確かに、日本はトイレ事情に恵まれている。しかし、過去の海外の文献等を調査する限りでは、国による排便障害への捉え方に大きな変化はなく、みんな同じ悩みを抱えているようである。
(文責:尾澤岬)
佐藤先生は、医学医療系の先生です。研究と同時に、臨床の現場にも携わっています。看護系の先生が、この教員プレゼンバトルで話すのは初めてでした。なので、どんな話をするのだろうか、と受講生はとても興味を持ったと思います。
そんな多くの受講生にとって、未知の世界である看護学への入り口として、佐藤先生はまず、「看護的な人間の捉え方」について紹介されました。看護に携わる人は、人間を分析的ではなく、トータルに、そして統合的に捉えているそうです。
佐藤先生が、今回発表された研究テーマは、「直腸がん前方切除術後の排便障害を評価」です。日本人の死因のトップは、がんと言われています。がんの中にも、胃がんや肺がんなど、様々な種類がありますが、「直腸がん」は、数あるがんのなかでも死因の上位に位置するものだそうです。
直腸がんの治療に、直腸の前方を切除するというものがあります。このような手術を受けた患者さんは、普段の生活に欠かせない排便に苦労することも多いそうです。例えば、私たちは、オナラか便のどちらが出そうなのかということを感覚的に分かります。なぜかというと、肛門付近に、両者を感知するサンプリングセンサーが付いているからだそうです。しかし、直腸がん前方切除術を受けた患者さんには、このセンサーは働かないため、大きな障害を伴います。
佐藤先生は、このような患者さんへのアンケートや、排便行動の定量的な評価、文献調査を駆使し、患者さんのQOLの向上を目指して日々研究しています。
人間をトータルに捉えるという看護の性格から、プレゼンには、悲しい局面や幸せな局面など、人間の感情的な内容が多く含まれていました。佐藤先生は、これらの喜怒哀楽を、発話の強弱や、トーンでみごとに表現していました。そして何より、患者さんへの愛が存分に伝わってくる発表でした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 海外によってトイレ事情が大きく異なる。海外に行くと、つくづく日本はトイレ事情に恵まれていると思う。すると、国によって排便障害への捉え方が変わってくるのではないか。(数理物質系の教員)
A.確かに、日本はトイレ事情に恵まれている。しかし、過去の海外の文献等を調査する限りでは、国による排便障害への捉え方に大きな変化はなく、みんな同じ悩みを抱えているようである。
(文責:尾澤岬) 教員プレゼンバトル2013 第六回講義概要
◆丹羽隆介 先生 「母から子へと与えられる栄養の底力〜ショウジョウバエを用いた研究から〜」
[プレゼン発表]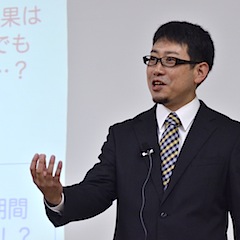 丹羽先生は発生遺伝学を専門に研究なさっている先生です。今回は、母から子へ伝わる遺伝の研究を、ショウジョウバエを例にわかりやすく紹介してくださいました。
生き物の体は、食べ物を食べ、消化し、栄養を吸収し、排出する、というサイクルを必要としています。このサイクルは代謝と呼ばれます。代謝は非常に複雑で、代謝をコントロールしているタンパク質に異常が生じると、重篤な病気を引き起こすケースがあります。そのため、代謝の研究は病気の原因を解明するための足がかりとして期待されています。
丹羽先生は、代謝の研究のモデル生物として、遺伝子がヒトとよく似ている黄色ショウジョウバエに着目しました。ショウジョウバエの発育にはコレステロールの代謝が必要で、コレステロールはNeverlandと呼ばれる酵素によって7−デヒドロコレステロールに変化し、最終的に成長に必要不可欠なステロイドホルモンへ変化します。丹羽先生は、Neverlandが欠乏するとショウジョウバエが成長できなくなることを明らかにしました。Neverlandが欠乏した母親が子供を生んだ場合、生まれた幼虫はNeverlandが欠乏するという情報が伝わってしまい、成長することができなくなってしまいます。
さて、Neverlandを欠乏したまま生まれてきた幼虫はこのまま一生を終えてしまうのでしょうか?この仮説を打破したのは、ずぼらな大学院生でした。その大学院生は、7−デヒドロコレステロールを混ぜたえさを与えたまま、数日ほったらかしにしていたそうです。後で調べてみると、Neverlandが欠乏した幼虫が成長していることが偶然わかりました。この発見を機転にいろいろと調べてみると、Neverlandが欠乏した親にえさを食べさせた場合でも、生まれてきた子供が成長できることが分かりました。これぞまさに「親から子へ伝わる栄養の底力」なのです。
代謝や遺伝の研究はモデル生物で行うことが多いが、得られた知見が必ずしもヒトに当てはあるものではないため、そこをどう解決していくかが大事であるとおっしゃっておりました。今後のご活躍に期待したいですね。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. (生物学専攻の大学院生)Neverlandが欠乏したショウジョウバエは、幼少のころ餌を摂取させると成長するということですが、ヒトのコレステロール欠乏症の場合でも同様の効果が期待できるのでしょうか?
A. その通りです。一般的な治癒はコレステロールを大量摂取します。しかし、生存期間を延長できても、生体の表現系は変えられません(指が6本になるなど)。また、母体に対してケアする方法もやられていません。なぜなら親は遺伝病を予測できないからです。近年では遺伝子診断で解決できる可能性は高まっています。昆虫の研究が哺乳類に対して反映されるかは未確認です。
Q. (コンピュータサイエンス専攻の大学院生)ショウジョウバエの研究結果をヒトにそのまま当てはめると。ヒトの場合7~8年寿命をのばすことになるとおっしゃっていましたが、本当にそうなるのでしょうか?
A. 詳細はまだよくわかっておりません。哺乳類は胎盤から栄養素が伝わりますが、とても特異的に選別されるため、親のコレステロールがそのまま伝わるとは言えません。また、ショウジョウバエの母体から子への栄養の伝搬過程もよくわかっていないのです。現在実験中で今後明らかにしていきたいです。
[種明かしディスカッション]
このコーナーは、プレゼン発表の極意や気を付けていることなどを伝授してもらいます。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
丹羽先生は発生遺伝学を専門に研究なさっている先生です。今回は、母から子へ伝わる遺伝の研究を、ショウジョウバエを例にわかりやすく紹介してくださいました。
生き物の体は、食べ物を食べ、消化し、栄養を吸収し、排出する、というサイクルを必要としています。このサイクルは代謝と呼ばれます。代謝は非常に複雑で、代謝をコントロールしているタンパク質に異常が生じると、重篤な病気を引き起こすケースがあります。そのため、代謝の研究は病気の原因を解明するための足がかりとして期待されています。
丹羽先生は、代謝の研究のモデル生物として、遺伝子がヒトとよく似ている黄色ショウジョウバエに着目しました。ショウジョウバエの発育にはコレステロールの代謝が必要で、コレステロールはNeverlandと呼ばれる酵素によって7−デヒドロコレステロールに変化し、最終的に成長に必要不可欠なステロイドホルモンへ変化します。丹羽先生は、Neverlandが欠乏するとショウジョウバエが成長できなくなることを明らかにしました。Neverlandが欠乏した母親が子供を生んだ場合、生まれた幼虫はNeverlandが欠乏するという情報が伝わってしまい、成長することができなくなってしまいます。
さて、Neverlandを欠乏したまま生まれてきた幼虫はこのまま一生を終えてしまうのでしょうか?この仮説を打破したのは、ずぼらな大学院生でした。その大学院生は、7−デヒドロコレステロールを混ぜたえさを与えたまま、数日ほったらかしにしていたそうです。後で調べてみると、Neverlandが欠乏した幼虫が成長していることが偶然わかりました。この発見を機転にいろいろと調べてみると、Neverlandが欠乏した親にえさを食べさせた場合でも、生まれてきた子供が成長できることが分かりました。これぞまさに「親から子へ伝わる栄養の底力」なのです。
代謝や遺伝の研究はモデル生物で行うことが多いが、得られた知見が必ずしもヒトに当てはあるものではないため、そこをどう解決していくかが大事であるとおっしゃっておりました。今後のご活躍に期待したいですね。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. (生物学専攻の大学院生)Neverlandが欠乏したショウジョウバエは、幼少のころ餌を摂取させると成長するということですが、ヒトのコレステロール欠乏症の場合でも同様の効果が期待できるのでしょうか?
A. その通りです。一般的な治癒はコレステロールを大量摂取します。しかし、生存期間を延長できても、生体の表現系は変えられません(指が6本になるなど)。また、母体に対してケアする方法もやられていません。なぜなら親は遺伝病を予測できないからです。近年では遺伝子診断で解決できる可能性は高まっています。昆虫の研究が哺乳類に対して反映されるかは未確認です。
Q. (コンピュータサイエンス専攻の大学院生)ショウジョウバエの研究結果をヒトにそのまま当てはめると。ヒトの場合7~8年寿命をのばすことになるとおっしゃっていましたが、本当にそうなるのでしょうか?
A. 詳細はまだよくわかっておりません。哺乳類は胎盤から栄養素が伝わりますが、とても特異的に選別されるため、親のコレステロールがそのまま伝わるとは言えません。また、ショウジョウバエの母体から子への栄養の伝搬過程もよくわかっていないのです。現在実験中で今後明らかにしていきたいです。
[種明かしディスカッション]
このコーナーは、プレゼン発表の極意や気を付けていることなどを伝授してもらいます。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆松本末男先生 「「ことばを育てる」~特別支援教育から~」
[プレゼン発表] 松本先生は筑波大学付属学校教育局の先生で、言語指導を専門に研究なさっています。教員プレゼンバトルに参加するために筑波キャンパスまでお越しいただきました。今回は、特別支援教育が必要な子供たちどのように言葉を教えるか、言語教育に関する生のお話をしてくださいました。
耳が聞こえない人にとっての最大の苦悩は、言語を習得するのがものすごく困難になることです。そのため、聴覚障害の人の中でしゃべれない人も多くいます。しかし、現実には聴覚障害者で普通に社会人として働いている人もいます。この差はどこから生まれるのでしょうか?答えは言語教育です。聴覚障害の子供に日本語をきちんとはなせるように教育することで、結果的にコミュニケーションがとれるようになります。
しかし、自閉症の子供へ言語を教えることはもっと厄介です。自閉症の子供は耳が聞こえるが、発言出来ない場合があります。自閉症の子供にコミュニケーションをとらせる術はあるのでしょうか?やはり答えは言語教育にありました。自閉症の子供たちに話し言葉があれば自分の意志表現が可能なことを気づかせてあげることが重要です。そのためにも、周囲の人々が子供の様子を注意深く見てやることが大事であるとおっしゃっていました。
松本さんは聴覚障害や自閉症の子供に言語を教えてきた経験から、その言語教育の方法はどちらも同じなのだと結論づけていました。詳しい内容は割愛させていただきます。最近では障害者への関心が薄まっている傾向にありますが、皆が豊かに暮らせるためにも、障害者への関心は日頃から持っておくべきだと松本さんは強く願っていました。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. (人文学専攻の大学院生)聴覚障害や自閉症の子供にとっても話し言葉は大切だとおっしゃっていましたが、松本さんの教えている技術で、どの程度まで話せるようになるのか?
A. 以前教えた聴覚障害の子供では、国立大学に在籍し、会社員や教員をしていました。いずれにせよ、聴覚障害者に関しては社会でふつうに過ごせる力は養うことができるでしょう。一方、自閉症の子供は自分の思いをしゃべれるようになる程度で、まだまだノウハウが不足しているのが現状です。
[種明かしディスカッション]
このコーナーは、プレゼン発表の極意や気を付けていることなどを伝授してもらいます。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
松本先生は筑波大学付属学校教育局の先生で、言語指導を専門に研究なさっています。教員プレゼンバトルに参加するために筑波キャンパスまでお越しいただきました。今回は、特別支援教育が必要な子供たちどのように言葉を教えるか、言語教育に関する生のお話をしてくださいました。
耳が聞こえない人にとっての最大の苦悩は、言語を習得するのがものすごく困難になることです。そのため、聴覚障害の人の中でしゃべれない人も多くいます。しかし、現実には聴覚障害者で普通に社会人として働いている人もいます。この差はどこから生まれるのでしょうか?答えは言語教育です。聴覚障害の子供に日本語をきちんとはなせるように教育することで、結果的にコミュニケーションがとれるようになります。
しかし、自閉症の子供へ言語を教えることはもっと厄介です。自閉症の子供は耳が聞こえるが、発言出来ない場合があります。自閉症の子供にコミュニケーションをとらせる術はあるのでしょうか?やはり答えは言語教育にありました。自閉症の子供たちに話し言葉があれば自分の意志表現が可能なことを気づかせてあげることが重要です。そのためにも、周囲の人々が子供の様子を注意深く見てやることが大事であるとおっしゃっていました。
松本さんは聴覚障害や自閉症の子供に言語を教えてきた経験から、その言語教育の方法はどちらも同じなのだと結論づけていました。詳しい内容は割愛させていただきます。最近では障害者への関心が薄まっている傾向にありますが、皆が豊かに暮らせるためにも、障害者への関心は日頃から持っておくべきだと松本さんは強く願っていました。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. (人文学専攻の大学院生)聴覚障害や自閉症の子供にとっても話し言葉は大切だとおっしゃっていましたが、松本さんの教えている技術で、どの程度まで話せるようになるのか?
A. 以前教えた聴覚障害の子供では、国立大学に在籍し、会社員や教員をしていました。いずれにせよ、聴覚障害者に関しては社会でふつうに過ごせる力は養うことができるでしょう。一方、自閉症の子供は自分の思いをしゃべれるようになる程度で、まだまだノウハウが不足しているのが現状です。
[種明かしディスカッション]
このコーナーは、プレゼン発表の極意や気を付けていることなどを伝授してもらいます。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆土井裕人先生 「宗教思想をいかに捉え、考えるか」
[プレゼン発表] 土井先生は宗教学を専門に研究なさっている先生です。今回は、宗教思想をいかにして捉えるかということに関して、お話ししてくださいました。
研究テーマは西洋古代の宗教思想についてです。そもそも宗教というものに学術性があるのかというところから話は始まり、宗教研究の難しさを訴えていました。しかし、古くから宗教は人間の根幹に関わっているため、その源流を問い直すことに非常に意義があると力説しておりました。まず神に似ることというテーマに基づいたプラトン主義が広まり、そのテーマを魂の乗り物という形で具現化する新プラトン主義が続きました。このような思想は現在まで語り継がれてきましたが、実際はあまり理解されていないのが現状です。土井先生は思想研究にも新展開が必要だと考え、コンピュータを利用して思想を可視化することに挑戦しました。文献をD3.js力学モデルを用いて解析し、得られたマッピングデータで思想を可視化するというものです。しかし、実際にはデータの解釈で議論が絶えず、可視化は非常に難航しているそうです。
土井先生は、宗教学を新しく切り開いていくテクノロジーを開拓していきたいとおっしゃっていました。私を含めほとんどの筑波大生は哲学になじみがないでしょうから、とても新鮮なプレゼンだと感じました。この感覚を毎回味わうことができる授業はおそらく教員プレゼンバトルだけでしょう。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. (生物学専攻の教員)思想の視覚化について、作業はテキストベースの言葉を抽出して、その関係を重みづけして、グラフ化するというものです、英文学でやられていることと本質的に一緒だと思います。思想の視覚化と表現されるのは妥当なのか?
A. おっしゃる通り、作業は一緒に見えます。しかし、思想研究として見たうえでどう役立たせうるのか、それをやってみたい。
[種明かしディスカッション]
このコーナーは、プレゼン発表の極意や気を付けていることなどを伝授してもらいます。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
(文責:栗之丸隆章)
土井先生は宗教学を専門に研究なさっている先生です。今回は、宗教思想をいかにして捉えるかということに関して、お話ししてくださいました。
研究テーマは西洋古代の宗教思想についてです。そもそも宗教というものに学術性があるのかというところから話は始まり、宗教研究の難しさを訴えていました。しかし、古くから宗教は人間の根幹に関わっているため、その源流を問い直すことに非常に意義があると力説しておりました。まず神に似ることというテーマに基づいたプラトン主義が広まり、そのテーマを魂の乗り物という形で具現化する新プラトン主義が続きました。このような思想は現在まで語り継がれてきましたが、実際はあまり理解されていないのが現状です。土井先生は思想研究にも新展開が必要だと考え、コンピュータを利用して思想を可視化することに挑戦しました。文献をD3.js力学モデルを用いて解析し、得られたマッピングデータで思想を可視化するというものです。しかし、実際にはデータの解釈で議論が絶えず、可視化は非常に難航しているそうです。
土井先生は、宗教学を新しく切り開いていくテクノロジーを開拓していきたいとおっしゃっていました。私を含めほとんどの筑波大生は哲学になじみがないでしょうから、とても新鮮なプレゼンだと感じました。この感覚を毎回味わうことができる授業はおそらく教員プレゼンバトルだけでしょう。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. (生物学専攻の教員)思想の視覚化について、作業はテキストベースの言葉を抽出して、その関係を重みづけして、グラフ化するというものです、英文学でやられていることと本質的に一緒だと思います。思想の視覚化と表現されるのは妥当なのか?
A. おっしゃる通り、作業は一緒に見えます。しかし、思想研究として見たうえでどう役立たせうるのか、それをやってみたい。
[種明かしディスカッション]
このコーナーは、プレゼン発表の極意や気を付けていることなどを伝授してもらいます。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
(文責:栗之丸隆章) 教員プレゼンバトル2013 第五回講義概要
◆生稲史彦先生 「開発生産性のディレンマ」
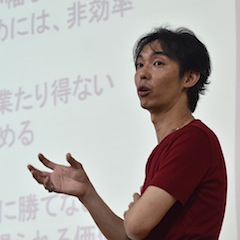 [プレゼン発表]
生稲先生は経営学の専門家です。今回は、生稲先生が取り組んでこられた、ゲームソフト企業を対象とした研究についてプレゼン発表をされました。
生稲先生が学生だった頃は、ちょうどテレビゲームが盛んになり出した時代で、生稲先生も、多くの男子学生と同様、テレビゲームにすっかりはまっていたそうです。ゲームを始めた頃は、次々と販売される新作に深い感動を覚えていたそうですが、だんだんと新作に対する新規性や、魅力を感じなくなり、遂にはつまらないと思うようになったそうです。そのため、「なぜ本当に新しいものが開発されなくなったのだろうか?」という疑問を生稲先生は持ちました。そして、この素朴な疑問を経営学の視点で解き明かそう、と思ったのが研究の出発点だそうです。
研究に着手しはじめ頃は、経営学の分野で既に確立しているメジャーな考え方を、そのままゲームソフト企業に当てはめる、という研究スタイルだったそうです。「知識こそが価値の源泉である」という、経営学のメジャーな考え方によれば、開発ノウハウを蓄積していくことこそが、ゲームソフト企業が競争優位を生み出すためのマネジメント法であることが結論されます。
しかし、「本当にそうなのか?」、と生稲先生は思ったそうです。確かに、経営学のメジャーな考え方(cool heads)からすれば、開発ノウハウの蓄積は企業にとって良いマネジメント法かもしれない。しかし実際には、「ゲームがつまらなくなった」、という個人的で確かな感覚(warm hearts)がある。そこで、cool headsではなくwarm heartsを優先し、そもそも経営学のメジャーな考え方を疑ってみる、という方向で研究を仕切り直したそうです。
そして新たに、「イノベーション」という視点で研究を見つめ直し、公刊資料や企業から得られたデータの収集など、地道な実証研究を展開され、遂にたどり着いたのが、「開発生産性のディレンマ」という考え方です。
「開発生産性のディレンマ」とは、開発ノウハウの蓄積を進めていくと、開発活動の効率化と同時に、類似性を優先する戦略に偏重してしまい、「新しいなにか」を創りだすことができなくなってしまう現象だと、生稲先生は言います。企業における開発ノウハウの蓄積なくしては、企業たり得ないことは確かですが、皮肉なことに、その開発ノウハウの蓄積が将来の可能性を狭めてしまうことを、このディレンマは主張します。
十数年かけて構築した理論を、わずか15分のプレゼンで発表するという、(生稲先生曰く)「無理な」発表でしたが、研究内容に対する自信に満ちた一語一句や、力強い身振り手振りから、十数年の研究の重みが十分に伝わってきました。そして、「cool heads」や「warm hearts」など、こだわって選び抜かれたフレーズが、プレゼンの魅力を引き立てており、自身がおっしゃる通り、生稲先生のプレゼンは正に、「総合芸(術)」でした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 私は一人のゲームファンとして、最近の日本のゲームソフトに新しさを感じない。日本のゲームソフト業界が、世界を驚かせるような、新しいものを開発できる見込みはあるか。(生命環境科学研究科の大学院生)
A. 私の理論に照らし合わせて言うと、新しいものが開発されるためには、企業間の競争ではなく、ゲームソフト業界への他の分野からの参入が必要だと思う。そのためには、ニューカマーを受け入れるような、業界のオープンネスが今後必要になると思う。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
[プレゼン発表]
生稲先生は経営学の専門家です。今回は、生稲先生が取り組んでこられた、ゲームソフト企業を対象とした研究についてプレゼン発表をされました。
生稲先生が学生だった頃は、ちょうどテレビゲームが盛んになり出した時代で、生稲先生も、多くの男子学生と同様、テレビゲームにすっかりはまっていたそうです。ゲームを始めた頃は、次々と販売される新作に深い感動を覚えていたそうですが、だんだんと新作に対する新規性や、魅力を感じなくなり、遂にはつまらないと思うようになったそうです。そのため、「なぜ本当に新しいものが開発されなくなったのだろうか?」という疑問を生稲先生は持ちました。そして、この素朴な疑問を経営学の視点で解き明かそう、と思ったのが研究の出発点だそうです。
研究に着手しはじめ頃は、経営学の分野で既に確立しているメジャーな考え方を、そのままゲームソフト企業に当てはめる、という研究スタイルだったそうです。「知識こそが価値の源泉である」という、経営学のメジャーな考え方によれば、開発ノウハウを蓄積していくことこそが、ゲームソフト企業が競争優位を生み出すためのマネジメント法であることが結論されます。
しかし、「本当にそうなのか?」、と生稲先生は思ったそうです。確かに、経営学のメジャーな考え方(cool heads)からすれば、開発ノウハウの蓄積は企業にとって良いマネジメント法かもしれない。しかし実際には、「ゲームがつまらなくなった」、という個人的で確かな感覚(warm hearts)がある。そこで、cool headsではなくwarm heartsを優先し、そもそも経営学のメジャーな考え方を疑ってみる、という方向で研究を仕切り直したそうです。
そして新たに、「イノベーション」という視点で研究を見つめ直し、公刊資料や企業から得られたデータの収集など、地道な実証研究を展開され、遂にたどり着いたのが、「開発生産性のディレンマ」という考え方です。
「開発生産性のディレンマ」とは、開発ノウハウの蓄積を進めていくと、開発活動の効率化と同時に、類似性を優先する戦略に偏重してしまい、「新しいなにか」を創りだすことができなくなってしまう現象だと、生稲先生は言います。企業における開発ノウハウの蓄積なくしては、企業たり得ないことは確かですが、皮肉なことに、その開発ノウハウの蓄積が将来の可能性を狭めてしまうことを、このディレンマは主張します。
十数年かけて構築した理論を、わずか15分のプレゼンで発表するという、(生稲先生曰く)「無理な」発表でしたが、研究内容に対する自信に満ちた一語一句や、力強い身振り手振りから、十数年の研究の重みが十分に伝わってきました。そして、「cool heads」や「warm hearts」など、こだわって選び抜かれたフレーズが、プレゼンの魅力を引き立てており、自身がおっしゃる通り、生稲先生のプレゼンは正に、「総合芸(術)」でした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 私は一人のゲームファンとして、最近の日本のゲームソフトに新しさを感じない。日本のゲームソフト業界が、世界を驚かせるような、新しいものを開発できる見込みはあるか。(生命環境科学研究科の大学院生)
A. 私の理論に照らし合わせて言うと、新しいものが開発されるためには、企業間の競争ではなく、ゲームソフト業界への他の分野からの参入が必要だと思う。そのためには、ニューカマーを受け入れるような、業界のオープンネスが今後必要になると思う。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆北将樹先生 「哺乳類の持つ毒の科学」
 [プレゼン発表]
北先生は、有機化学が専門の先生です。生物の持つ毒を有機化学の視点で研究しています。
ハチ、サソリ、フグなどは毒を持つ生き物の代表格ですが、哺乳類にも毒を持つ生き物がいるそうです。それが北先生の研究対象である、トガリネズミの仲間とカモノハシです。
トガリネズミは、主に夜行性でミミズや昆虫を主食にしているかわいらしい動物です。しかし、愛くるしい姿形に似つかわしくなく、唾液に毒が含まれていることが報告されていました。
一言に毒と言っても、その正体は、低分子やタンパク質など様々で、より詳細を知るためには、化学物質として毒を単離し、分子構造を明らかにすることが必要になります。このことこそが、北先生が得意とする、有機化学の出番です。北先生は世界で初めて哺乳類の毒成分の構造を明らかにした、この分野の第一線の研究者です。
化学者の研究現場は、実験室だというイメージがありますが、北先生は実験室だけに留まらず、生態学者とタッグを組んでフィールドに出かけます。今回、日本とキューバの共同研究プロジェクトにより、「ソレノドン」という生態の分かっていない未知の生き物の捕獲と唾液の採取を目指し、キューバまで行かれました。ほとんどソレノドンに関する情報の無い中、遂にソレノドンの個体の捕獲と唾液の採集に成功し、大きな話題となりました。現在このプロジェクトは、得られた唾液から、毒の構造を解析中だそうです。
北先生は、タンパク質の話から、ソレノドンのかわいらしい行動の動画まで、緩急をつけたプレゼンで観客を魅了しました。また、ミクロな分子構造の化学の話から、動物行動、さらには化石や進化の話まで、様々なスケールの科学が毒というキーワードの下に凝集しており、非常に学際的な研究であることが印象に残りました。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 北先生の研究は、医療関係に役立つのでは?
A. 新規な毒の化学的な解明は、薬理学や、神経学などの基礎研究に寄与し、さらには、痛みに関する創薬にも繋がる。
Q. 毒を持っている動物が、自分の毒が効かないのはなぜか?
A. タンパク毒は、自分自身の毒が血液中に入ってしまわないようになっている。逆に血液中に入ってしまえば死んでしまう。トガリネズミが共食いする際、相手の毒で死んでしまうこともある。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
[プレゼン発表]
北先生は、有機化学が専門の先生です。生物の持つ毒を有機化学の視点で研究しています。
ハチ、サソリ、フグなどは毒を持つ生き物の代表格ですが、哺乳類にも毒を持つ生き物がいるそうです。それが北先生の研究対象である、トガリネズミの仲間とカモノハシです。
トガリネズミは、主に夜行性でミミズや昆虫を主食にしているかわいらしい動物です。しかし、愛くるしい姿形に似つかわしくなく、唾液に毒が含まれていることが報告されていました。
一言に毒と言っても、その正体は、低分子やタンパク質など様々で、より詳細を知るためには、化学物質として毒を単離し、分子構造を明らかにすることが必要になります。このことこそが、北先生が得意とする、有機化学の出番です。北先生は世界で初めて哺乳類の毒成分の構造を明らかにした、この分野の第一線の研究者です。
化学者の研究現場は、実験室だというイメージがありますが、北先生は実験室だけに留まらず、生態学者とタッグを組んでフィールドに出かけます。今回、日本とキューバの共同研究プロジェクトにより、「ソレノドン」という生態の分かっていない未知の生き物の捕獲と唾液の採取を目指し、キューバまで行かれました。ほとんどソレノドンに関する情報の無い中、遂にソレノドンの個体の捕獲と唾液の採集に成功し、大きな話題となりました。現在このプロジェクトは、得られた唾液から、毒の構造を解析中だそうです。
北先生は、タンパク質の話から、ソレノドンのかわいらしい行動の動画まで、緩急をつけたプレゼンで観客を魅了しました。また、ミクロな分子構造の化学の話から、動物行動、さらには化石や進化の話まで、様々なスケールの科学が毒というキーワードの下に凝集しており、非常に学際的な研究であることが印象に残りました。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 北先生の研究は、医療関係に役立つのでは?
A. 新規な毒の化学的な解明は、薬理学や、神経学などの基礎研究に寄与し、さらには、痛みに関する創薬にも繋がる。
Q. 毒を持っている動物が、自分の毒が効かないのはなぜか?
A. タンパク毒は、自分自身の毒が血液中に入ってしまわないようになっている。逆に血液中に入ってしまえば死んでしまう。トガリネズミが共食いする際、相手の毒で死んでしまうこともある。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆手塚太郎先生 「疎性に基づく情報処理」
 [プレゼン発表]
手塚先生は図書館情報メディア系の先生です。あの有名な、「やってみよう研究所」の所長でもあります。今回は、コンピュータサイエンスの世界で話題となっている、「疎性に基づく情報処理」について発表されました。
コンピュータサイエンスの究極の目標は、コンピュータに人間と同じ思考をさせることだと手塚先生は言います。そのため、人間を含めた生物の情報処理の仕組みが解明されると、その仕組みがコンピュータサイエンスに応用されることが多いそうです。「物事を認識する」、という一見コンピュータにとって複雑で困難な課題も、生物がやっている方法から学びとることで、克服することができます。その一つの例が、生物の神経系における「疎性」と呼ばれる性質の、コンピュータの情報処理への応用です。
手塚先生はまず、生物が物事を認識する際の、神経系の仕組みを非常に明快に説明されました。我々生物の脳の中には、ネットワークで繋がった沢山の神経細胞が存在しています。ある一つの認識に対する情報処理過程には、これらのネットワーク中の“数多く”の神経細胞が関与していると想像できるでしょう。しかし実際には、“少数の”(疎らな)神経細胞だけが活動しているそうです。これが「疎性」と呼ばれる性質です。このように、神経系が「疎性」的な活動をするメリットは、蓄えられる情報量の増加や、省エネ等が考えられるそうです。
そしてこの「疎性」的な仕組みを、コンピュータの情報処理に応用することができます。
例として、コンピュータによる画像処理を紹介されました。コンピュータで扱うデジタル画像を、数学のベクトルで表現します。その際に、多くのベクトル成分がゼロとなるように情報を扱うことで、生物系でみられる「疎性」な情報処理が可能になります。このことが、膨大なデータを処理する際に、計算コストを下げることが可能になるそうです。
手塚先生は、テンポよくリズミカルな発表をされ、話の流れが非常に明快でした。また、誰よりも楽しそうに発表されるため、研究のおもしろさが存分に伝わってきました。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 手塚先生は、「人間の脳とコンピュータは同じである」というが、同じリンゴであっても、鮮度の違いなど、それぞれの質感みたいなものがあるので、こういった感覚はコンピュータでは捉えられないと思う。つまり、人間の脳をコンピュータで再現することは難しいのでは。(教育学専攻の大学院生)
A. それは単に、コンピュータが質感を学習できていないからである。学習させることができれば、リンゴの鮮度も判断できると思う。赤ちゃんも生まれていきなり「おばあちゃん」を認識するわけではない。
Q. しかし、人間の脳には個人差みたいなものもあるので、これらはコンピュータで捉えられないのでは。(教育学専攻の大学院生)
A. 最近インターネット上で学習する人工知能が開発されている。この方法なら、非常に多くのことを学習可能であるので、コンピュータが質感や、個人差みたいなものも理解する日が来るかもしれない。
人間の脳VSコンピュータ、というとても刺激的な討論になりました。
この議論に関する手塚先生の立場がhttp://yattemiyou.net/archive/machines.htmlに代弁されていると思いますのでこちらもご覧下さい。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
(文責:尾澤岬)
[プレゼン発表]
手塚先生は図書館情報メディア系の先生です。あの有名な、「やってみよう研究所」の所長でもあります。今回は、コンピュータサイエンスの世界で話題となっている、「疎性に基づく情報処理」について発表されました。
コンピュータサイエンスの究極の目標は、コンピュータに人間と同じ思考をさせることだと手塚先生は言います。そのため、人間を含めた生物の情報処理の仕組みが解明されると、その仕組みがコンピュータサイエンスに応用されることが多いそうです。「物事を認識する」、という一見コンピュータにとって複雑で困難な課題も、生物がやっている方法から学びとることで、克服することができます。その一つの例が、生物の神経系における「疎性」と呼ばれる性質の、コンピュータの情報処理への応用です。
手塚先生はまず、生物が物事を認識する際の、神経系の仕組みを非常に明快に説明されました。我々生物の脳の中には、ネットワークで繋がった沢山の神経細胞が存在しています。ある一つの認識に対する情報処理過程には、これらのネットワーク中の“数多く”の神経細胞が関与していると想像できるでしょう。しかし実際には、“少数の”(疎らな)神経細胞だけが活動しているそうです。これが「疎性」と呼ばれる性質です。このように、神経系が「疎性」的な活動をするメリットは、蓄えられる情報量の増加や、省エネ等が考えられるそうです。
そしてこの「疎性」的な仕組みを、コンピュータの情報処理に応用することができます。
例として、コンピュータによる画像処理を紹介されました。コンピュータで扱うデジタル画像を、数学のベクトルで表現します。その際に、多くのベクトル成分がゼロとなるように情報を扱うことで、生物系でみられる「疎性」な情報処理が可能になります。このことが、膨大なデータを処理する際に、計算コストを下げることが可能になるそうです。
手塚先生は、テンポよくリズミカルな発表をされ、話の流れが非常に明快でした。また、誰よりも楽しそうに発表されるため、研究のおもしろさが存分に伝わってきました。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 手塚先生は、「人間の脳とコンピュータは同じである」というが、同じリンゴであっても、鮮度の違いなど、それぞれの質感みたいなものがあるので、こういった感覚はコンピュータでは捉えられないと思う。つまり、人間の脳をコンピュータで再現することは難しいのでは。(教育学専攻の大学院生)
A. それは単に、コンピュータが質感を学習できていないからである。学習させることができれば、リンゴの鮮度も判断できると思う。赤ちゃんも生まれていきなり「おばあちゃん」を認識するわけではない。
Q. しかし、人間の脳には個人差みたいなものもあるので、これらはコンピュータで捉えられないのでは。(教育学専攻の大学院生)
A. 最近インターネット上で学習する人工知能が開発されている。この方法なら、非常に多くのことを学習可能であるので、コンピュータが質感や、個人差みたいなものも理解する日が来るかもしれない。
人間の脳VSコンピュータ、というとても刺激的な討論になりました。
この議論に関する手塚先生の立場がhttp://yattemiyou.net/archive/machines.htmlに代弁されていると思いますのでこちらもご覧下さい。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
(文責:尾澤岬) 教員プレゼンバトル2013 第四回講義概要
◆中園長新先生 『 「いま」を生きるための情報教育 』
 [プレゼン発表]
中園先生は、教育学域で「情報教育」に関する研究をしている先生です。正確には教員という立場ではありませんが、TGN独自の学内調査で、非常にアクティブな方であるという情報を受け、この度プレゼンターをお願いしました。
情報教育と聞くと、中高生時代に受けたエクセルやパワーポイントなどの実習を思い出す人が多いと思います。しかしながら、パソコン操作の実習が情報教育の現場で主要なテーマとなっているのは、現代だからに過ぎない、と中園先生は言います。パソコンの全く無かった戦国時代であれば、のろしの回数を数えることが情報教育の重要な役目かもしれません。このように、パソコン・ケータイなどの機器の使い方や、現代という時代を離れて存在する、情報教育の本質について中園先生は模索されています。
では一体、情報教育の本質とは何でしょうか?それは、コミュニケーションに行きつくのではないか、と中園先生は考えているそうです。このことを、次の巧みな例えで説明されました。
カップ麺の作り方を初心者に教えたいとします。すると多くの人が、1. お湯を沸かす、2. フタを開ける、3. お湯を注ぐ、4. ・・・。というように作り方を伝えると思います。しかしながら実際には、フタを開ける前にビニールをはがすことが必要です。また、ラーメン系または焼きそば系であるかによって、ソースを入れる順番が重要になってきます。この例から分かるように、現実にやり取りされる情報には多くの「行間」が存在します。情報過多と言われる現代ですが、生きていくためにはこの行間を読み取る能力が必要とされます。そして、この能力を鍛えることが情報教育の重要な役目ではないかと提案されました。
中園先生は、今年度のプレゼンターの方々の中では抜群に若く、エネルギッシュな発表をされました。特にカップ麺の件では、会場にカップ麺を持参し、ビニールを破るアクションをされたことが、非常に印象に残りました。情報がデジタルに伝えられることが多い中で、実世界に実物を導入して伝えることに、大いにリアリティを感じました。仮想世界の台頭で見失われがちな情報教育の本質を、ある種体現しているようなプレゼンでした。
また中園先生は、プレゼンの補足を先生自身のホームページに掲載してくださっているようです。こちらもご覧ください。http://zono.e4serv.net/weblog/
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. なぜ現状では、高校などでの情報教育は、パワーポイントやエクセルの使い方を教えるといったパソコン教室化してしまっているのか。(畜産を専門に研究している大学院生)
A. このようなありきたりの情報教育になってしまっている理由は二つある。一つは、教える側の専門性にある。情報教育について専門的な指導ができる高校教員は少ない。もう一つは、実社会で即戦力となる人材を育成することが要求されているため、実社会で役立つパソコンスキルの習得が早急に望まれているからだと思われる。
Q. とは言うものの、個人的には高校でのパソコン教育は非常に役に立っている。それを変える理由はあるか。(植物育種を専門とする大学院生)
A. パソコンスキルだけでなく、情報化社会が持つ闇の部分も知る必要があると思う。例えば、なぜfacebookが無料であるか、といった知識も今後生きていく上で必要であると思う。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
[プレゼン発表]
中園先生は、教育学域で「情報教育」に関する研究をしている先生です。正確には教員という立場ではありませんが、TGN独自の学内調査で、非常にアクティブな方であるという情報を受け、この度プレゼンターをお願いしました。
情報教育と聞くと、中高生時代に受けたエクセルやパワーポイントなどの実習を思い出す人が多いと思います。しかしながら、パソコン操作の実習が情報教育の現場で主要なテーマとなっているのは、現代だからに過ぎない、と中園先生は言います。パソコンの全く無かった戦国時代であれば、のろしの回数を数えることが情報教育の重要な役目かもしれません。このように、パソコン・ケータイなどの機器の使い方や、現代という時代を離れて存在する、情報教育の本質について中園先生は模索されています。
では一体、情報教育の本質とは何でしょうか?それは、コミュニケーションに行きつくのではないか、と中園先生は考えているそうです。このことを、次の巧みな例えで説明されました。
カップ麺の作り方を初心者に教えたいとします。すると多くの人が、1. お湯を沸かす、2. フタを開ける、3. お湯を注ぐ、4. ・・・。というように作り方を伝えると思います。しかしながら実際には、フタを開ける前にビニールをはがすことが必要です。また、ラーメン系または焼きそば系であるかによって、ソースを入れる順番が重要になってきます。この例から分かるように、現実にやり取りされる情報には多くの「行間」が存在します。情報過多と言われる現代ですが、生きていくためにはこの行間を読み取る能力が必要とされます。そして、この能力を鍛えることが情報教育の重要な役目ではないかと提案されました。
中園先生は、今年度のプレゼンターの方々の中では抜群に若く、エネルギッシュな発表をされました。特にカップ麺の件では、会場にカップ麺を持参し、ビニールを破るアクションをされたことが、非常に印象に残りました。情報がデジタルに伝えられることが多い中で、実世界に実物を導入して伝えることに、大いにリアリティを感じました。仮想世界の台頭で見失われがちな情報教育の本質を、ある種体現しているようなプレゼンでした。
また中園先生は、プレゼンの補足を先生自身のホームページに掲載してくださっているようです。こちらもご覧ください。http://zono.e4serv.net/weblog/
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. なぜ現状では、高校などでの情報教育は、パワーポイントやエクセルの使い方を教えるといったパソコン教室化してしまっているのか。(畜産を専門に研究している大学院生)
A. このようなありきたりの情報教育になってしまっている理由は二つある。一つは、教える側の専門性にある。情報教育について専門的な指導ができる高校教員は少ない。もう一つは、実社会で即戦力となる人材を育成することが要求されているため、実社会で役立つパソコンスキルの習得が早急に望まれているからだと思われる。
Q. とは言うものの、個人的には高校でのパソコン教育は非常に役に立っている。それを変える理由はあるか。(植物育種を専門とする大学院生)
A. パソコンスキルだけでなく、情報化社会が持つ闇の部分も知る必要があると思う。例えば、なぜfacebookが無料であるか、といった知識も今後生きていく上で必要であると思う。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆金久保利之先生 『 コンクリート構造物の地震被害とその対策 』
 [プレゼン発表]
金久保先生は、コンクリートの構造や強度に関する研究を専門にされています。近年の地震による建物の被害を受け、今後の地震に対する備えはますます重要になってきています。そんな中で、今注目されている金久保先生にプレゼンをお願いしました。
まず金久保先生は、東日本大震災で倒壊した建物の写真を紹介されました。メリハリの利いた文字だけのスライドで発表された中園先生とは対照的に、写真中心の構成で話を展開されました。完全に潰れてしまった日本家屋や、天井がごっそり落ちてしまった体育館が、地震に対する建物の脆弱性を物語っていました。東日本大震災では、原子力や津波による被害が大きく取り上げられていますが、ここ茨城県では、地震の揺れによる建物への直接的なダメージが主要な被害の形態だそうです。今後も油断できない大地震への備えとして、地震の揺れに耐えることのできる建物が望まれます。
ところで、そもそも建物が壊れるのはどうしてでしょうか。金久保先生は、原点に立ち返った疑問を聴衆に投げかけました。率直に考えると、「建物の強度を地震の強さが上回ったから」、と結論したくなります。実は、「重力」の影響が大きいそうです。このことを、円柱とおもりでできた模式図を用いて説明されました。地面に立てた細長い円柱の先に、おもりをバランスよく乗せます。いざ地震が来て横揺れが起こると、円柱はたわみます。するとおもりに働く重力を支えきれなり、倒壊します。重力が建物に与える影響は、非常に複雑なメカニズムのようですが、単純化された模式図を導入したことで、大づかみに理解することができました。
プレゼンの最後に、金久保先生の実際の研究タイトル「鉄筋コンクリート構造の耐荷性状と変形性能」を宣言されて発表は終わりました。つまり、金久保先生は、自身の研究内容には触れず、発表の15分を全てイントロに割り当てました。金久保先生曰く、「発表タイトルが理解してもらえれば充分」、とのことです。このプレゼン構成には驚きましたが、質疑応答の際に受講生から踏み込んだ質問が数多く出ました。つまり、「掴み」は大成功だったようです。異分野向けのプレゼンの場で、聴衆とのインタラクションを活発にするには、今回の金久保先生のようなスタイルが有効ではないでしょうか。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 今回の地震で、実家の建物が倒壊してしまった。原因は地盤沈下だったようだ。もうこのような経験はしたくないので、将来土地を買う時の指針のようなものを教えてほしい。(システム情報工学研究科の大学院生)
過去に川・沼・池であった土地は液状化現象が起きやすい。地名に川や池が付く場所は昔そうであった場合が多い。より詳しく調べたい場合は、国土地理院に行って昔の地図を調べればよい。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
[プレゼン発表]
金久保先生は、コンクリートの構造や強度に関する研究を専門にされています。近年の地震による建物の被害を受け、今後の地震に対する備えはますます重要になってきています。そんな中で、今注目されている金久保先生にプレゼンをお願いしました。
まず金久保先生は、東日本大震災で倒壊した建物の写真を紹介されました。メリハリの利いた文字だけのスライドで発表された中園先生とは対照的に、写真中心の構成で話を展開されました。完全に潰れてしまった日本家屋や、天井がごっそり落ちてしまった体育館が、地震に対する建物の脆弱性を物語っていました。東日本大震災では、原子力や津波による被害が大きく取り上げられていますが、ここ茨城県では、地震の揺れによる建物への直接的なダメージが主要な被害の形態だそうです。今後も油断できない大地震への備えとして、地震の揺れに耐えることのできる建物が望まれます。
ところで、そもそも建物が壊れるのはどうしてでしょうか。金久保先生は、原点に立ち返った疑問を聴衆に投げかけました。率直に考えると、「建物の強度を地震の強さが上回ったから」、と結論したくなります。実は、「重力」の影響が大きいそうです。このことを、円柱とおもりでできた模式図を用いて説明されました。地面に立てた細長い円柱の先に、おもりをバランスよく乗せます。いざ地震が来て横揺れが起こると、円柱はたわみます。するとおもりに働く重力を支えきれなり、倒壊します。重力が建物に与える影響は、非常に複雑なメカニズムのようですが、単純化された模式図を導入したことで、大づかみに理解することができました。
プレゼンの最後に、金久保先生の実際の研究タイトル「鉄筋コンクリート構造の耐荷性状と変形性能」を宣言されて発表は終わりました。つまり、金久保先生は、自身の研究内容には触れず、発表の15分を全てイントロに割り当てました。金久保先生曰く、「発表タイトルが理解してもらえれば充分」、とのことです。このプレゼン構成には驚きましたが、質疑応答の際に受講生から踏み込んだ質問が数多く出ました。つまり、「掴み」は大成功だったようです。異分野向けのプレゼンの場で、聴衆とのインタラクションを活発にするには、今回の金久保先生のようなスタイルが有効ではないでしょうか。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 今回の地震で、実家の建物が倒壊してしまった。原因は地盤沈下だったようだ。もうこのような経験はしたくないので、将来土地を買う時の指針のようなものを教えてほしい。(システム情報工学研究科の大学院生)
過去に川・沼・池であった土地は液状化現象が起きやすい。地名に川や池が付く場所は昔そうであった場合が多い。より詳しく調べたい場合は、国土地理院に行って昔の地図を調べればよい。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆三谷純先生 『 コンピュータが拓く新時代の折り紙設計 』
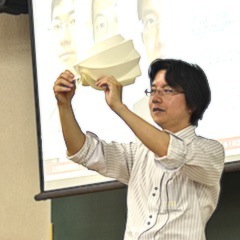 [プレゼン発表]
三谷先生は、コンピュータグラフィックスが専門の先生です。今回の発表では、コンピュータによる折り紙の設計についてプレゼンして頂きました。私たち日本人にとってなじみ深い折り紙ですが、その歴史は古く、1797年には折り鶴の様々なバリエーションをまとめた文献が刊行されているそうです。このような伝統ある折り紙と、コンピュータの接点はどこにあるのでしょうか。
折り鶴を、もう一度平坦な紙に展開してみましょう。すると、山・谷の折れ線によってできた複雑な幾何学模様が見えます。そして再度、山・谷の線に従って折り込むと、さきほどと全く同じ折り鶴が再現できます。つまり、折り鶴と山・谷の折れ線の幾何学的パターンは一対一に対応します。そして、このような幾何学的なパターンの処理はコンピュータが得意とするところです。ここが折り紙とコンピュータの接点のようです。誰もが驚くような、複雑で美しい構造を折るのは、折り紙の熟練者でないとなかなか折れません。そこで三谷先生は、誰でも簡単に複雑で美しい立体的構造を折ることができる折り紙ソフトウェアを開発しました。プレゼン発表では、ソフトウェアの実演と、完成した実物を披露されました。このようなコンピュータを駆使した折り紙設計では、一見難しい曲面的な構造さえ折ることができるそうです。
以上の折り紙研究の反響は大きく、ファッションショーで使用されたり、数学の教科書の表紙にも採用されたそうです。また、「ものをコンパクトに畳む」という応用性が人工衛星のソーラーパネルをはじめ、多くの分野で注目されているそうです。
三谷先生は、研究内容もさることながら、流れるような口調から圧巻のプレゼンを披露されました。プレゼンスライドは、「最初と最後が一番見られる」という考えから、最初のスライドにtwitterのアカウント「@jmitani」を表示されていました。今回のプレゼンバトルを機にフォロワーを30人くらい増やしたいとのことです。みなさんもフォローしてみてはどうでしょうか。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 折り紙の世界では、紙を切るのは御法度か?(構造エネルギー専攻の教員)
A. 折り紙の定義はいろいろあって、研究者によってまちまちだが、私は切らない流儀で研究している。しかし一方で、紙のかたちは自由に選んでいる。
Q. そのように折り紙の定義が様々だと、定義によって性質に違いが表れそうだ。(構造エネルギー専攻の教員)
A. その通りだ。例えば、切り目を入れる/入れないの流儀の違いで、応用性が変わってくる。防塵カバーの折り方をデザインしたい場合、切り目を入れない流儀でデザインしないといけない。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
[プレゼン発表]
三谷先生は、コンピュータグラフィックスが専門の先生です。今回の発表では、コンピュータによる折り紙の設計についてプレゼンして頂きました。私たち日本人にとってなじみ深い折り紙ですが、その歴史は古く、1797年には折り鶴の様々なバリエーションをまとめた文献が刊行されているそうです。このような伝統ある折り紙と、コンピュータの接点はどこにあるのでしょうか。
折り鶴を、もう一度平坦な紙に展開してみましょう。すると、山・谷の折れ線によってできた複雑な幾何学模様が見えます。そして再度、山・谷の線に従って折り込むと、さきほどと全く同じ折り鶴が再現できます。つまり、折り鶴と山・谷の折れ線の幾何学的パターンは一対一に対応します。そして、このような幾何学的なパターンの処理はコンピュータが得意とするところです。ここが折り紙とコンピュータの接点のようです。誰もが驚くような、複雑で美しい構造を折るのは、折り紙の熟練者でないとなかなか折れません。そこで三谷先生は、誰でも簡単に複雑で美しい立体的構造を折ることができる折り紙ソフトウェアを開発しました。プレゼン発表では、ソフトウェアの実演と、完成した実物を披露されました。このようなコンピュータを駆使した折り紙設計では、一見難しい曲面的な構造さえ折ることができるそうです。
以上の折り紙研究の反響は大きく、ファッションショーで使用されたり、数学の教科書の表紙にも採用されたそうです。また、「ものをコンパクトに畳む」という応用性が人工衛星のソーラーパネルをはじめ、多くの分野で注目されているそうです。
三谷先生は、研究内容もさることながら、流れるような口調から圧巻のプレゼンを披露されました。プレゼンスライドは、「最初と最後が一番見られる」という考えから、最初のスライドにtwitterのアカウント「@jmitani」を表示されていました。今回のプレゼンバトルを機にフォロワーを30人くらい増やしたいとのことです。みなさんもフォローしてみてはどうでしょうか。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 折り紙の世界では、紙を切るのは御法度か?(構造エネルギー専攻の教員)
A. 折り紙の定義はいろいろあって、研究者によってまちまちだが、私は切らない流儀で研究している。しかし一方で、紙のかたちは自由に選んでいる。
Q. そのように折り紙の定義が様々だと、定義によって性質に違いが表れそうだ。(構造エネルギー専攻の教員)
A. その通りだ。例えば、切り目を入れる/入れないの流儀の違いで、応用性が変わってくる。防塵カバーの折り方をデザインしたい場合、切り目を入れない流儀でデザインしないといけない。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。 教員プレゼンバトル2013 第三回講義概要
◆津田和彦先生 「テキストマイニングとその応用」
[プレゼン発表]
 津田先生は、東京キャンパスにあるビジネスサイエンス系の先生です。今回は、教員プレゼンバトルに参加するために筑波キャンパスまでお越しいただきました。筑波キャンパスで学ぶ私たちにとって、今まで東京キャンパスとはあまり接点がなかったと思います。今後TGNでは、東京キャンパスも積極的に巻き込んで筑波大学全体を学術的に盛り上げていきたいと思っています。さて、プレゼン内容に話を戻します。津田先生は、日本語や英語などのいわゆる自然言語(コンピュータ言語と比較してこのように呼ぶ)で書かれた文章の中から、内容を計算機を用いて抽出する研究を行っています。人間でない計算機からすると、ネット上の文章やメールは無機質な文字の羅列にあたるため、そこから内容を引き出すなんて信じられません。しかしそれを可能にするのが、膨大なデータの中から規則性を掘りだす、データマイニングという計算機科学の手法です。データマイニングの手法では、様々な形でやりとりされる文書を主語と述語に分解し、高度な計算を駆使して文章内容をくみ取ります。特に、文末の述語に注目すると、その文章が肯定的な内容なのか、あるいは否定的な内容であるのか大体判定できるそうです。ところで、ネット上の文章やメールのやりとりには顔文字がよく使われます。携帯メールで活用している方も多いのではないでしょうか。意外にもこの顔文字が、文章の内容を読み取るのに結構役に立つそうです。例えば文末に、(;`´)oという顔文字があったとします。この時、顔文字の中の“`´”に注目することで、怒りを表す内容であることを引き出すことができるそうです。こうした研究技術は、試験的に宿泊サイトの批評の解析などにも応用されているようです。ネット上でやりとりされる文章がますます増えている昨今、津田先生の研究は今後大きな応用の可能性を秘めていると感じました。津田先生のプレゼンは、常に聴衆を見ながら語りかけ、私たちと呼吸を合わせながら発表するスタイルでした。何十人もの受講生を相手にしているにも関わらず、あたかも一対一で話を聞いているかのような錯覚を覚え、プレゼンに自然と引き込まれていきました。「聴衆とリズムを合わせる」という感覚が、プレゼンを生き生きと魅力的なものにするということを認識しました。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 「部屋は広いけど料理はちょっと。。。」というように、日本語には真意を明らかにせずに、相手に空気を読ませるような文章表現がある。このような表現から内容をくみ取るようなことは可能だろうか。(文学を専攻する大学院生)
A. 「。。。」(3点リーダー)という文章表現の場合、 直前の単語でほとんど意味が決定されている。今の例だと、直前の「ちょっと」が文章全体を否定的な意味に導いている。このような3点リーダーに関しては、90%くらいの正答率で文意を特定できる。
Q. それでは、他にも嫌味や皮肉を文章からくみ取ることは可能か。
A. これらはなかなか難しい。しかし、顔文字の解析が役に立つ場合が多い。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
津田先生は、東京キャンパスにあるビジネスサイエンス系の先生です。今回は、教員プレゼンバトルに参加するために筑波キャンパスまでお越しいただきました。筑波キャンパスで学ぶ私たちにとって、今まで東京キャンパスとはあまり接点がなかったと思います。今後TGNでは、東京キャンパスも積極的に巻き込んで筑波大学全体を学術的に盛り上げていきたいと思っています。さて、プレゼン内容に話を戻します。津田先生は、日本語や英語などのいわゆる自然言語(コンピュータ言語と比較してこのように呼ぶ)で書かれた文章の中から、内容を計算機を用いて抽出する研究を行っています。人間でない計算機からすると、ネット上の文章やメールは無機質な文字の羅列にあたるため、そこから内容を引き出すなんて信じられません。しかしそれを可能にするのが、膨大なデータの中から規則性を掘りだす、データマイニングという計算機科学の手法です。データマイニングの手法では、様々な形でやりとりされる文書を主語と述語に分解し、高度な計算を駆使して文章内容をくみ取ります。特に、文末の述語に注目すると、その文章が肯定的な内容なのか、あるいは否定的な内容であるのか大体判定できるそうです。ところで、ネット上の文章やメールのやりとりには顔文字がよく使われます。携帯メールで活用している方も多いのではないでしょうか。意外にもこの顔文字が、文章の内容を読み取るのに結構役に立つそうです。例えば文末に、(;`´)oという顔文字があったとします。この時、顔文字の中の“`´”に注目することで、怒りを表す内容であることを引き出すことができるそうです。こうした研究技術は、試験的に宿泊サイトの批評の解析などにも応用されているようです。ネット上でやりとりされる文章がますます増えている昨今、津田先生の研究は今後大きな応用の可能性を秘めていると感じました。津田先生のプレゼンは、常に聴衆を見ながら語りかけ、私たちと呼吸を合わせながら発表するスタイルでした。何十人もの受講生を相手にしているにも関わらず、あたかも一対一で話を聞いているかのような錯覚を覚え、プレゼンに自然と引き込まれていきました。「聴衆とリズムを合わせる」という感覚が、プレゼンを生き生きと魅力的なものにするということを認識しました。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. 「部屋は広いけど料理はちょっと。。。」というように、日本語には真意を明らかにせずに、相手に空気を読ませるような文章表現がある。このような表現から内容をくみ取るようなことは可能だろうか。(文学を専攻する大学院生)
A. 「。。。」(3点リーダー)という文章表現の場合、 直前の単語でほとんど意味が決定されている。今の例だと、直前の「ちょっと」が文章全体を否定的な意味に導いている。このような3点リーダーに関しては、90%くらいの正答率で文意を特定できる。
Q. それでは、他にも嫌味や皮肉を文章からくみ取ることは可能か。
A. これらはなかなか難しい。しかし、顔文字の解析が役に立つ場合が多い。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆遠藤靖典先生 「クラスタリングによる知識発見」
[プレゼン発表]
 遠藤先生が専門とするクラスタリングとは、人間の手には負えないような沢山のデータを、類似なもの同士に分類する計算機科学の手法のことです。みなさんお気づきだと思いますが、遠藤先生とひとつ前の発表者の津田先生の研究分野は非常に近いと思います。現在、データマイニングやクラスタリングは、ビジネス、シス情と研究科を越えて活発に研究されており、今後大注目の研究分野のようです。さて、私たちが普段何か物事を分類するときには、分類するための指針のようなものを使っていると思います。(例えば、タコとイカを分類するのは“足の数”でしょうか?)このような指針のことを計算機科学の分野では、「教師」と呼ぶそうです。しかし、いつでも適切な教師が存在するとは限りません。また、無理に教師を設定しようとすると、誤った分類を導きかねません。そこで、遠藤先生は、「教師なし」で分類を可能にするクラスタリング手法について紹介されました。つまり、データのみの情報を用いて分類を行うことができるそうです。研究事例として、twitter上でのデマ情報の検出について発表されました。twitterは、誰でも気軽に情報発信ができ、伝達スピードは既存のどのメディアよりも速いことが知られています。そして、東日本大震災では、災害時の情報伝達に非常に優れているということが明らかになりました。しかし一方で、twitter上に多くのデマが生まれ、それが混乱を引き起こすことが浮き彫りとなりました。そのため、今後より有用な情報伝達メディアとして扱うために、害のあるデマと本当に有用なニュースを見分けることが要求されます。そこで、遠藤先生はクラスタリングの研究手法を応用し、twitter上のデマ検出に取り組みました。具体的には、twitterの情報のみを使って(教師なしで)、「デマ」と「本当のニュース」を分類する手法を提案されました。その結果、なんと80%の精度で、デマと本当のニュースを分類することができるようになったそうです。遠藤先生は発表中、ステージを飛び出して会場を自由に行き来し、躍動感溢れる発表を展開されました。そのため、計算機科学という緻密な研究内容の発表にも関わらず、研究に対する情熱が存分に伝わってきました。講演後の休憩時間中も、質疑応答のコーナーでは物足りなかった学生たちが列をなして質問している姿が印象的でした。
[質疑応答コーナー]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. twitterの文章が肯定または否定的な内容を含むことと、そのtweetがデマであることはどのように対応するのか。(物理学専攻の大学院生)
A. デマには危機感を煽ることを目的にしたものが多いので、否定的な内容がデマの特徴の一つとなる。そのため、デマの同定には、文章中の否定的な部分の抽出が有用となる。
Q. 実用上、不安感を煽るような否定的デマは早急に同定する必要があるだろう。逆に「私はダイエットに成功した」みたいな肯定的デマは広まってもあまり害はない。(笑)
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
遠藤先生が専門とするクラスタリングとは、人間の手には負えないような沢山のデータを、類似なもの同士に分類する計算機科学の手法のことです。みなさんお気づきだと思いますが、遠藤先生とひとつ前の発表者の津田先生の研究分野は非常に近いと思います。現在、データマイニングやクラスタリングは、ビジネス、シス情と研究科を越えて活発に研究されており、今後大注目の研究分野のようです。さて、私たちが普段何か物事を分類するときには、分類するための指針のようなものを使っていると思います。(例えば、タコとイカを分類するのは“足の数”でしょうか?)このような指針のことを計算機科学の分野では、「教師」と呼ぶそうです。しかし、いつでも適切な教師が存在するとは限りません。また、無理に教師を設定しようとすると、誤った分類を導きかねません。そこで、遠藤先生は、「教師なし」で分類を可能にするクラスタリング手法について紹介されました。つまり、データのみの情報を用いて分類を行うことができるそうです。研究事例として、twitter上でのデマ情報の検出について発表されました。twitterは、誰でも気軽に情報発信ができ、伝達スピードは既存のどのメディアよりも速いことが知られています。そして、東日本大震災では、災害時の情報伝達に非常に優れているということが明らかになりました。しかし一方で、twitter上に多くのデマが生まれ、それが混乱を引き起こすことが浮き彫りとなりました。そのため、今後より有用な情報伝達メディアとして扱うために、害のあるデマと本当に有用なニュースを見分けることが要求されます。そこで、遠藤先生はクラスタリングの研究手法を応用し、twitter上のデマ検出に取り組みました。具体的には、twitterの情報のみを使って(教師なしで)、「デマ」と「本当のニュース」を分類する手法を提案されました。その結果、なんと80%の精度で、デマと本当のニュースを分類することができるようになったそうです。遠藤先生は発表中、ステージを飛び出して会場を自由に行き来し、躍動感溢れる発表を展開されました。そのため、計算機科学という緻密な研究内容の発表にも関わらず、研究に対する情熱が存分に伝わってきました。講演後の休憩時間中も、質疑応答のコーナーでは物足りなかった学生たちが列をなして質問している姿が印象的でした。
[質疑応答コーナー]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. twitterの文章が肯定または否定的な内容を含むことと、そのtweetがデマであることはどのように対応するのか。(物理学専攻の大学院生)
A. デマには危機感を煽ることを目的にしたものが多いので、否定的な内容がデマの特徴の一つとなる。そのため、デマの同定には、文章中の否定的な部分の抽出が有用となる。
Q. 実用上、不安感を煽るような否定的デマは早急に同定する必要があるだろう。逆に「私はダイエットに成功した」みたいな肯定的デマは広まってもあまり害はない。(笑)
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆岩井宏暁先生 「イネの細胞壁をデザインする」
[プレゼン発表]
 岩井先生は、植物生理学、植物細胞生物学を専門に研究している先生です。今回は、バイオ燃料への応用を目指した、イネの細胞壁に関する基礎研究について発表して頂きました。岩井先生は、「植物のかたちはどうやってできあがるのだろうか」という素朴な疑問から植物の細胞の研究をはじめられたそうです。植物はレンガのように積まれた細胞で作られており、その細胞をがっちりと支えているのが細胞壁です。この細胞壁が植物のかたちづくりに果たす役割を調べる一方で、逆に細胞壁を自由にデザインすることで、何かに役立つ植物を作ることができます。そこで注目されたのがバイオ燃料への応用です。地球上のエネルギー問題が深刻化してきているなかで、バイオ燃料にかかる期待は日々増すばかりです。しかし、バイオ燃料をもっと実用的なものにするには、まだまだ克服しなければならない問題点が多いそうです。その中でも、茎などの食べられない部分をより効率よく燃焼できる作物を開発することが求められています。そこで岩井先生は、バイオ燃料の源となる、細胞壁中の「セルロース」を増やす研究に着手されました。試行錯誤の結果、セルロース同士を結ぶ“ワイヤー”役である「ヘミセルロース」の発現を抑えると、セルロースの量が増加することを発見しました。さらに、今回発見したセルロースを多く含むイネは、丈夫で病気にもなりにくい性質を併せ持つことも分かったそうです。以上の性質は、バイオ燃料の効率化に向けた大きな示唆を与えるそうです。「植物のかたちはどうなっているのだろうか」、という基礎的な問題意識が、エネルギー問題に関わるバイオ燃料の研究へと結実していく展開にワクワクさせられました。「わたしも研究頑張ろう!」と思った受講生も多かったのではないでしょうか。また岩井先生は、専門外の人にとっては全く想像できない細胞壁の中の世界を、ビルの構造に例えて説明されました。そのことで、呪文のように聞こえる「セルロース」や「ヘミセルロース」も身近なものに感じることができました。やはり、専門外の人には、分かりやすい対象に例える技術が大事であると痛感しました。
[質疑応答コーナー]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. イネ全体の内、食べられない部分をバイオ燃料に活用する一方で、食べる部分に遺伝子の組み換えに伴う何らかの負の影響が出たりしないか。(システム情報工学研究科の院生)
A. 本研究の特色は、ヘミセルロースの量を抑えるとセルロースが増加するという、細胞自身の機能を使うことにある。また、本研究はトウモロコシのように直近の実用化を目指したものではなく、何十年も先を見越した基礎研究に位置づけられる。なので、食べる部分とバイオ燃料を兼ねるためにイネの研究をしているという意図よりも、研究に適したモデル生物としてのイネの役割に注目している。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
文責:尾澤岬
岩井先生は、植物生理学、植物細胞生物学を専門に研究している先生です。今回は、バイオ燃料への応用を目指した、イネの細胞壁に関する基礎研究について発表して頂きました。岩井先生は、「植物のかたちはどうやってできあがるのだろうか」という素朴な疑問から植物の細胞の研究をはじめられたそうです。植物はレンガのように積まれた細胞で作られており、その細胞をがっちりと支えているのが細胞壁です。この細胞壁が植物のかたちづくりに果たす役割を調べる一方で、逆に細胞壁を自由にデザインすることで、何かに役立つ植物を作ることができます。そこで注目されたのがバイオ燃料への応用です。地球上のエネルギー問題が深刻化してきているなかで、バイオ燃料にかかる期待は日々増すばかりです。しかし、バイオ燃料をもっと実用的なものにするには、まだまだ克服しなければならない問題点が多いそうです。その中でも、茎などの食べられない部分をより効率よく燃焼できる作物を開発することが求められています。そこで岩井先生は、バイオ燃料の源となる、細胞壁中の「セルロース」を増やす研究に着手されました。試行錯誤の結果、セルロース同士を結ぶ“ワイヤー”役である「ヘミセルロース」の発現を抑えると、セルロースの量が増加することを発見しました。さらに、今回発見したセルロースを多く含むイネは、丈夫で病気にもなりにくい性質を併せ持つことも分かったそうです。以上の性質は、バイオ燃料の効率化に向けた大きな示唆を与えるそうです。「植物のかたちはどうなっているのだろうか」、という基礎的な問題意識が、エネルギー問題に関わるバイオ燃料の研究へと結実していく展開にワクワクさせられました。「わたしも研究頑張ろう!」と思った受講生も多かったのではないでしょうか。また岩井先生は、専門外の人にとっては全く想像できない細胞壁の中の世界を、ビルの構造に例えて説明されました。そのことで、呪文のように聞こえる「セルロース」や「ヘミセルロース」も身近なものに感じることができました。やはり、専門外の人には、分かりやすい対象に例える技術が大事であると痛感しました。
[質疑応答コーナー]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. イネ全体の内、食べられない部分をバイオ燃料に活用する一方で、食べる部分に遺伝子の組み換えに伴う何らかの負の影響が出たりしないか。(システム情報工学研究科の院生)
A. 本研究の特色は、ヘミセルロースの量を抑えるとセルロースが増加するという、細胞自身の機能を使うことにある。また、本研究はトウモロコシのように直近の実用化を目指したものではなく、何十年も先を見越した基礎研究に位置づけられる。なので、食べる部分とバイオ燃料を兼ねるためにイネの研究をしているという意図よりも、研究に適したモデル生物としてのイネの役割に注目している。
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
文責:尾澤岬
教員プレゼンバトル2013 第二回講義概要
◆掛谷英紀先生 「プロパガンダを工学する」
[プレゼン発表]
 「プロパガンダ」とは政治やマスコミ関係でよく出てくる用語です。広辞苑で調べてみると、『特定の政治的考えを押し付けるための宣伝』という意味らしいです。それを工学するって一体どういうことでしょうか。残念ながら私には全く想像が出来ませんでした。そんな予想外なタイトルに惹かれた方も多かったと思います。思えば、「新聞やテレビなどのマスメディアは思想的に中立ではなく、ある程度のバイアスがかかっている」というような言論を耳にします。実際には誰しも感じていることだと思うのですが、なかなか説明することは容易ではありません。このいわゆる、「言論のバイアス」を機械学習という工学の手法を使って定量的に評価しよう、と目論むのが掛谷先生の研究でした。機械学習とは大雑把に言えば、膨大なデータから意味のある情報を抜き出して整理する工学の手法のことです。では、この機械学習を使ってどのように思想的バイアスが暴けるのでしょうか。掛谷先生はいくつも研究事例を挙げながら説明されました。特に興味を引いたのは、新聞に書かれた文章だけから新聞社(読売、毎日、日経など)を当てるという研究です。文章に含まれる単語の出現パターンを機械学習によって整理し、どの新聞社の文章であるのか分類しながら推論するとのことです。「まさかそんなことは出来ないだろう」、と一見感じますが、予想以上に的中率の精度は高く、いかに各新聞社の言論に思想的なバイアスがかかっているか、という事実が浮き彫りになりました。その他にも、政治家の書いた文章だけから政党を分類することさえ出来てしまうそうです。また、このような研究成果を応用して「将来は選挙支援にも役立てたい」と目標を語っていただけました。発表の仕方は明快で、文系理系を問わず、全ての専攻の方が興味を持てるように非常に工夫されたプレゼン発表でした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. このような研究をやっていて、外部から圧力がかかったりしないか?(生命環境の大学院生)
A. 今のところは大丈夫だ。私がもっと有名になって、何か政治的なことを提言しはじめると、外部から圧力がかかってくるかもしれない(笑)。(掛谷先生)
Q. 生物の進化の過程で、種というものはどんどん分化していく。そしてそれらは系統樹として書き表せるが、掛谷先生の開発した機械学習の手法で、政党の分化や、政党の系統樹的な解析はできるか。(生物系の教員)
A. そのようなことは可能だ。例えば、選挙日が近づくと離党する議員がよく現れるが、彼らの文章を解析すれば、いつ離党するのか予測できるかもしれない。(掛谷先生)
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
「プロパガンダ」とは政治やマスコミ関係でよく出てくる用語です。広辞苑で調べてみると、『特定の政治的考えを押し付けるための宣伝』という意味らしいです。それを工学するって一体どういうことでしょうか。残念ながら私には全く想像が出来ませんでした。そんな予想外なタイトルに惹かれた方も多かったと思います。思えば、「新聞やテレビなどのマスメディアは思想的に中立ではなく、ある程度のバイアスがかかっている」というような言論を耳にします。実際には誰しも感じていることだと思うのですが、なかなか説明することは容易ではありません。このいわゆる、「言論のバイアス」を機械学習という工学の手法を使って定量的に評価しよう、と目論むのが掛谷先生の研究でした。機械学習とは大雑把に言えば、膨大なデータから意味のある情報を抜き出して整理する工学の手法のことです。では、この機械学習を使ってどのように思想的バイアスが暴けるのでしょうか。掛谷先生はいくつも研究事例を挙げながら説明されました。特に興味を引いたのは、新聞に書かれた文章だけから新聞社(読売、毎日、日経など)を当てるという研究です。文章に含まれる単語の出現パターンを機械学習によって整理し、どの新聞社の文章であるのか分類しながら推論するとのことです。「まさかそんなことは出来ないだろう」、と一見感じますが、予想以上に的中率の精度は高く、いかに各新聞社の言論に思想的なバイアスがかかっているか、という事実が浮き彫りになりました。その他にも、政治家の書いた文章だけから政党を分類することさえ出来てしまうそうです。また、このような研究成果を応用して「将来は選挙支援にも役立てたい」と目標を語っていただけました。発表の仕方は明快で、文系理系を問わず、全ての専攻の方が興味を持てるように非常に工夫されたプレゼン発表でした。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. このような研究をやっていて、外部から圧力がかかったりしないか?(生命環境の大学院生)
A. 今のところは大丈夫だ。私がもっと有名になって、何か政治的なことを提言しはじめると、外部から圧力がかかってくるかもしれない(笑)。(掛谷先生)
Q. 生物の進化の過程で、種というものはどんどん分化していく。そしてそれらは系統樹として書き表せるが、掛谷先生の開発した機械学習の手法で、政党の分化や、政党の系統樹的な解析はできるか。(生物系の教員)
A. そのようなことは可能だ。例えば、選挙日が近づくと離党する議員がよく現れるが、彼らの文章を解析すれば、いつ離党するのか予測できるかもしれない。(掛谷先生)
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆卯城 祐司 「だから英語は面白い!」
[プレゼン発表]
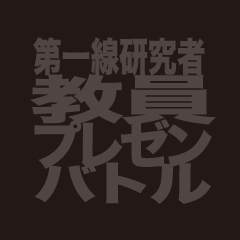 卯城先生は、英語教授法について研究している先生です。誰もが一度はお世話になった、有名な英語の教材の作成なんかにも携わっておられます。今回のプレゼン発表では、英語を学ぶことで楽しめる面白いトピックをたくさん紹介されました。例えば、「big」と「large」って、一見そっくりな単語ですが、ちょっとしたイメージの違いがあるそうです。bigには主観的なイメージが、そしてlargeには客観的なイメージをネイティブは感じているそうです。それゆえに、「ビッグマック」という商品名が放つ響きにはちゃんと意味があり、「ラージマック」では表現としてダメなのだそうです。今回の卯城先生のプレゼン発表で、新しく英単語を学ぶ際に意識すべき事が増えてしまったと感じるかもしれません。しかし、「実用的な英語」を駆使する上でその単語のニュアンスを把握することは重要であり、将来、海外で活躍する「グローバルな人材」になりたい方には非常に有意義な情報だったのではないでしょうか。話は変わりますが、個人的に印象に残ったのはプレゼンスタイルです。卯城先生は、聴衆に疑問を投げかける際に、30秒ほど隣の席同士で相談させる時間を設けました。私は当初、なぜわざわざ隣と相談させるのだろうか、と疑問に感じていましたが、後で腑に落ちてしまいました。プレゼン中にも関わらず会場内でガヤガヤと話させることで、場内の雰囲気のギアチェンジを引き起こしたのです。その後は、卯城先生のちょっとしたジョークにも会場が大いに反応し、プレゼンは爆笑の渦に包まれました。このことを卯城先生は意図して狙っていたのでしょうか?「だから卵城先生は面白い!」。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. アメリカ英語とか、イギリス英語、またはインド訛りなど、様々な英語の発音があるが、我々日本人はどういった発音をめざせばいいのか?(リスク工学専攻の大学院生)
A. 本当の答えはわからない。昔は、アメリカやイギリス英語を目指したが、現在は様々な英語発音に対して、それぞれ同様に価値があると考えられている。そのことを反映して、Englishesという単語もあるくらいだ。(卯城先生)
Q. 日本人の英語発音はネイティブにとって聞き取りやすいのか?(人間総合科学研究科の大学院生)
A. 日本人の英語発音はフラットで聞き取りにくいらしい。ネイティブの英語には、リズムがある。日本人にとってインド人の英語はなんとなく訛っていて聞き取りにくいイメージがあるようだが、ネイティブにとっては、日本人よりもインド人の英語の方が、リズムがあって聞き取りやすいらしい。(卯城先生)
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
卯城先生は、英語教授法について研究している先生です。誰もが一度はお世話になった、有名な英語の教材の作成なんかにも携わっておられます。今回のプレゼン発表では、英語を学ぶことで楽しめる面白いトピックをたくさん紹介されました。例えば、「big」と「large」って、一見そっくりな単語ですが、ちょっとしたイメージの違いがあるそうです。bigには主観的なイメージが、そしてlargeには客観的なイメージをネイティブは感じているそうです。それゆえに、「ビッグマック」という商品名が放つ響きにはちゃんと意味があり、「ラージマック」では表現としてダメなのだそうです。今回の卯城先生のプレゼン発表で、新しく英単語を学ぶ際に意識すべき事が増えてしまったと感じるかもしれません。しかし、「実用的な英語」を駆使する上でその単語のニュアンスを把握することは重要であり、将来、海外で活躍する「グローバルな人材」になりたい方には非常に有意義な情報だったのではないでしょうか。話は変わりますが、個人的に印象に残ったのはプレゼンスタイルです。卯城先生は、聴衆に疑問を投げかける際に、30秒ほど隣の席同士で相談させる時間を設けました。私は当初、なぜわざわざ隣と相談させるのだろうか、と疑問に感じていましたが、後で腑に落ちてしまいました。プレゼン中にも関わらず会場内でガヤガヤと話させることで、場内の雰囲気のギアチェンジを引き起こしたのです。その後は、卯城先生のちょっとしたジョークにも会場が大いに反応し、プレゼンは爆笑の渦に包まれました。このことを卯城先生は意図して狙っていたのでしょうか?「だから卵城先生は面白い!」。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. アメリカ英語とか、イギリス英語、またはインド訛りなど、様々な英語の発音があるが、我々日本人はどういった発音をめざせばいいのか?(リスク工学専攻の大学院生)
A. 本当の答えはわからない。昔は、アメリカやイギリス英語を目指したが、現在は様々な英語発音に対して、それぞれ同様に価値があると考えられている。そのことを反映して、Englishesという単語もあるくらいだ。(卯城先生)
Q. 日本人の英語発音はネイティブにとって聞き取りやすいのか?(人間総合科学研究科の大学院生)
A. 日本人の英語発音はフラットで聞き取りにくいらしい。ネイティブの英語には、リズムがある。日本人にとってインド人の英語はなんとなく訛っていて聞き取りにくいイメージがあるようだが、ネイティブにとっては、日本人よりもインド人の英語の方が、リズムがあって聞き取りやすいらしい。(卯城先生)
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
◆山本洋平先生 「分子集積材料による新しい光・電子機能発現」
[プレゼン発表]
 山本先生は、超分子化学という分野の研究をしている先生です。導入部では、化学が専門ではない学生も対象にして、化学とはどういう学問なのか基本的な説明をしてくださいました。誰もが「化学」と聞いて想像する原子。その原子を並べたのがあの一見無機質に見えてしまう周期表ですが、なんと山本先生は、各元素に日本のアニメキャラが描かれたイメージ破りの周期表を紹介されました。この作戦に、思わず(多くの)受講生は度肝を抜かれました。山本先生の作戦勝ちですね。お見事です。さて、化学では様々な分子を作るうえで、原子と原子の間の結合が重要な役割を果たします。とりわけ、共有結合という非常に丈夫な結合が有名です。しかし、共有結合よりももっと弱い結合でも、多様で魅力的な物質を作り出すことができるというのです。特に、山本先生が研究している、超分子とは、分子同士がゆるやかな結合で繋がった分子の集合体のことです。超分子は、結合のゆるやかさ故に、温度に応じて勝手に分子が積みあがるという性質を持ちます。その性質を最大限に用いた「自己組織化」のアニメーション映像は圧巻でした。単に、水と油に馴染みやすい両親媒性分子を溶媒の中に入れるだけで、東京スカイツリー顔負けの見事な建造物が勝手に組みあがってしまいました。山本先生曰く、これらの超分子が見せる性質を巧みに利用し、有機エレクトロ二クスに応用するのが目標だとのことです。山本先生のあっと驚くような発想による研究成果が、私たちの身近なデバイスにも使用される日が来るでしょう。そんな日が待ち遠しいですね。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. エレクトロニクスというと金属のイメージが強いが、有機エレクトロニクスは何がうれしいのか?(数理物質科学研究科の大学院生)
A. 有機分子は金属に比べて、軽くて柔らかいので非常に扱いやすい。さらに、金属を使わないということで資源の節約にもなる。(山本先生)
Q. 新しい材料を開発すると、研究の段階では無害と判断されても、後に応用されるようになってから毒性などが見つかったりはしないか。(システム情報工学研究科の大学院生)
A. 今のところない。私の研究は基礎研究に位置づけられ、応用として皆さんの生活に生かされるには、もう何ステップもの応用研究が必要だ。その間に毒性などの検証がなされるだろう。(山本先生)
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
文責:尾澤岬
山本先生は、超分子化学という分野の研究をしている先生です。導入部では、化学が専門ではない学生も対象にして、化学とはどういう学問なのか基本的な説明をしてくださいました。誰もが「化学」と聞いて想像する原子。その原子を並べたのがあの一見無機質に見えてしまう周期表ですが、なんと山本先生は、各元素に日本のアニメキャラが描かれたイメージ破りの周期表を紹介されました。この作戦に、思わず(多くの)受講生は度肝を抜かれました。山本先生の作戦勝ちですね。お見事です。さて、化学では様々な分子を作るうえで、原子と原子の間の結合が重要な役割を果たします。とりわけ、共有結合という非常に丈夫な結合が有名です。しかし、共有結合よりももっと弱い結合でも、多様で魅力的な物質を作り出すことができるというのです。特に、山本先生が研究している、超分子とは、分子同士がゆるやかな結合で繋がった分子の集合体のことです。超分子は、結合のゆるやかさ故に、温度に応じて勝手に分子が積みあがるという性質を持ちます。その性質を最大限に用いた「自己組織化」のアニメーション映像は圧巻でした。単に、水と油に馴染みやすい両親媒性分子を溶媒の中に入れるだけで、東京スカイツリー顔負けの見事な建造物が勝手に組みあがってしまいました。山本先生曰く、これらの超分子が見せる性質を巧みに利用し、有機エレクトロ二クスに応用するのが目標だとのことです。山本先生のあっと驚くような発想による研究成果が、私たちの身近なデバイスにも使用される日が来るでしょう。そんな日が待ち遠しいですね。
[質疑応答]
質疑応答では、異分野間のコミュニケーションらしい議論が繰り広げられました。特に白熱したやりとりを紹介します。
Q. エレクトロニクスというと金属のイメージが強いが、有機エレクトロニクスは何がうれしいのか?(数理物質科学研究科の大学院生)
A. 有機分子は金属に比べて、軽くて柔らかいので非常に扱いやすい。さらに、金属を使わないということで資源の節約にもなる。(山本先生)
Q. 新しい材料を開発すると、研究の段階では無害と判断されても、後に応用されるようになってから毒性などが見つかったりはしないか。(システム情報工学研究科の大学院生)
A. 今のところない。私の研究は基礎研究に位置づけられ、応用として皆さんの生活に生かされるには、もう何ステップもの応用研究が必要だ。その間に毒性などの検証がなされるだろう。(山本先生)
[種明かしディスカッション]
種明かしディスカッションのコーナーでは、プレゼン発表の極意や、気を付けていることなどを教えてもらったり、根掘り葉掘り質問攻めにするコーナーです。毎回、目からうろこの情報ばかりですが、これは実際会場に来て聴講した人の特権ということで、ここでは公表しません。
文責:尾澤岬